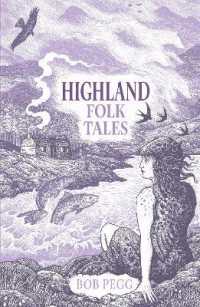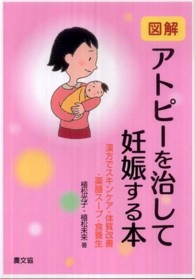出版社内容情報
すぐキレル若者、学級崩壊など、子どものこころから他人を思いやる気持ちがどんどん失われてきています。しかし人を思いやるこころは、一朝一夕には育ちません。どこかの知事が言うように、道徳教育を強化すれば解決する問題ではないのです。それは決して教えることはできず、幼いときから、自分の気持ちを身近な大人たちに十分に受けとめてもらった経験が育むものであることを、本書は保育の場での長い年月をかけたていねいな観察から明らかにしました。たくさんの事例から、保母さん、保父さん、子育て中の親が子どもの気持ちをどう受け止めたらよいか、具体的なヒントも豊富です。
「思いやり」の気持ちが育つためには、親や保育者が「思いやり」につながる子どもの気持ちの育ちを見守っていくことが大切です。それこそ、小さな赤ちゃんの頃から、ゆっくり時間をかけて育つのです。突然、「思いやり」の気持ちが育つわけではありません。赤ちゃんの頃は、とくにまわりの大人からたくさんの愛情ややさしさを受けることから始まります。しかし、その頃からすでに、赤ちゃんは単なる受身の存在ではありません。お互いの気持ちのやりとりを、きちんと感じとっています。赤ちゃんの頃から、母親に対して、もしくは保育者にたいして、子どもは「思いを遣る」ことを体験し始めます。(「第1章 「思いやり」をとらえる」より)
-------------------------------------------------------
【関連書籍】
『 自閉症 』 藤居学、神谷栄治著 (定価1995円 2007.5月)
『 エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学 』 岡本依子ほか著 (定価1995円 2004)
『 保育のための発達心理学 』 藤崎眞知代ほか著 (定価1995円 1998)
【新 刊】
『 二歳半という年齢 』 久保田正人著 (定価2310円 初版1993を復刊)
内容説明
子どもを観る眼、受けとめる眼。育むとは教え込むことではない…それは自ら「受容」と「共感」の眼をもつことから始まる。多数の実際例で見る、思いやりが育っていくすがた。
目次
第1章 「思いやり」をとらえる
第2章 「思いやり」行動の基盤を育む
第3章 「思いやり」行動の芽生え
第4章 幼児の「思いやり」行動をとらえる
第5章 幼児の「思いやり」行動観察の発展に向けて―横断的にみる
第6章 「思いやり」が豊かに育つ保育とは
第7章 「思いやり」を研究する方々のために
-

- 電子書籍
- プレーボール! ~プロ野球審判員物語~
-

- 和書
- 玻璃の舞姫 コバルト文庫