内容説明
戦後復興時に新しく生まれ変わった保育所は、未来を展望した国民の切なる願いの結晶であった。しかし、その後の保育政策は乳幼児の子育てを家族の責任に追いやり、入所できる子どもたちを限定してきた。1990年代以降、少子化を迎え女性の社会参加に応えようとしている日本は、保育所を国民生活にとって欠かすことのできない施設に位置づけた。1994年に子どもの権利条約を批准した日本。保護者の働く権利だけでなく、子どもの権利を保障する保育政策はどうあるべきか。その方向性をさぐる。
目次
序章 本書のねらいと視点
第1章 保育制度の成立と修正―戦後改革期:戦後~1950年代中頃
第2章 保育政策の「充実」と家庭保育原則―高度経済成長期:1950年代中頃~1970年代中頃
第3章 保育政策の「修正」と行政改革―低成長期:1970年代中頃~1980年代
第4章 保育政策の「転換」と保育改革―構造改革期:1990年代以降
終章 子どもの権利を保障する保育政策に向けて
著者等紹介
中村強士[ナカムラツヨシ]
1973年生まれ。2008年佛教大学大学院社会学研究科社会学・社会福祉学専攻博士後期課程修了。社会学博士。社会福祉士。現在、学校法人セムイ学園東海医療福祉専門学校専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
和田 悠
0
戦後保育政策を政府文書を読み解くことで時系列的に追った著書。これまでの類書との違いがよくわからないが(ジェンダー化・商品化だけでは弱い)、便利な本であり、労作であることは疑い得ない。ただ、政策を論じるにはもう少し政策を作成する人間の思想や所属、立ち位置、時代背景に焦点を当てる必要があるかなと思った。保育政策を社会史・社会政策史として論じるためには何が必要か。著者と一緒に考えて行きたいと思った。幼保一体化論に焦点をもっとあてて書き(読み)直しても面白い。経営者団体のロビー活動の実態や論点とかも知りたいなあ。2011/09/14
-

- 電子書籍
- 悪の組織の求人広告(話売り) #19 …
-
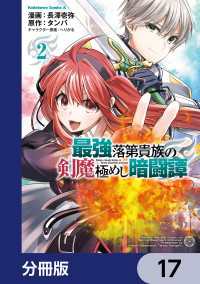
- 電子書籍
- 最強落第貴族の剣魔極めし暗闘譚【分冊版…
-
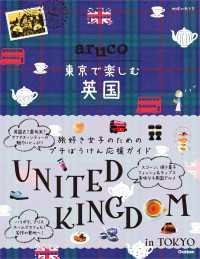
- 電子書籍
- aruco 東京で楽しむ英国 地球の歩…
-
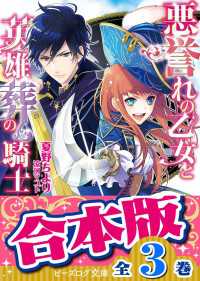
- 電子書籍
- 【合本版】悪誉れの乙女と英雄葬の騎士 …





