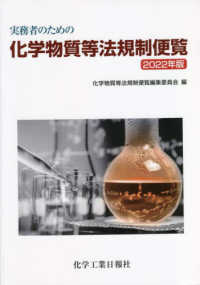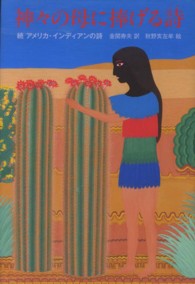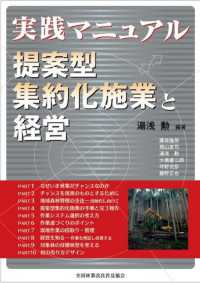内容説明
『源氏物語』の女君の中でも特に「内面がない」とみなされがちな人物、女三の宮。しかし先入観を排除してその言葉に耳を傾ければ、現代の女性にも似通うその人物像が明らかになる。これまで見過ごされてきた女三の宮の内面、内なる声とは。
目次
1 女三の宮の「内面」の物語(「なかったことにされた内面」;父と娘の物語;自己意識の発生と消去)
2 女三の宮の「内面」は描かれない?(「内面」とは何か?;女三の宮の内面)
3 『源氏物語』は「女」の物語か?(「女」は「男」を愛すべき?;「女」は子どもを愛すべき?;「私」は「女」なのか)
4 女三の宮の現代性(森茉莉『甘い蜜の部屋』と『源氏物語』;“女性作家”のセクシャリティ)
著者等紹介
西原志保[ニシハラシホ]
1980年香川県に生まれる。2003年同志社大学文学部文化学科卒業。2009年名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期課程修了、博士(文学)。人間文化研究機構国立国語研究所広報室非常勤研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
8
これまで「内面がない」と見なされてきた『源氏物語』の女三の宮に、もともと男女関係に無関心であったのが、柏木事件を経て性愛や妊娠・出産への嫌悪を自覚し、出家を経て父のもとに戻ることによって男女関係からの離脱を図るという「内面」やその推移を読み取れるとする。これまで否定的に見られていた女三の宮の人物像について、特に「女性性」の面からは現代的な感覚が読み取れるのだというところが面白い。2018/03/03
鳩羽
6
内面が描かれていないというのは、今時の小説への批評でも言われることだが、女三の宮は本当に内面が無かったのか、女三の宮の言葉や歌から推測する。自分の歴史を時系列で辿ることができ、自分の外界と内側の区別ができ、外界から得た刺激を自らの内で変化させ、それを表現できるのが、内面を持ち〈あはれ〉を知る大人の振る舞いだろう。だが、女三の宮はそういう形での自我は持っておらず、不快な男との経験から初めて自我らしきものを持ったとも言える。それが現代的かどうかは分からないが、多様性を考えるとき、現代の方が親和性は強いだろう。2018/02/05
maekoo
4
女三宮の持つ精神的内面構造を心理学的な観点から分析した論文です。 紫の上や藤壺の構造論や精神史研究は別の論者の著書で読んでいましたが女三宮は珍しいので読みました。 原文の例を挙げながら女三宮の内面がどう動き変化して行ったか読み解けます。 現代で言えばスマホを観ながら歩く女子高生みたいな幼い心象風景を醸し出す女三宮が柏木事件を通じて何を思いどう動いたかが良く解ります。 普通の男性に恋愛感情を抱かず、父性への依存が甚だしい女三宮は現代女性に通じる部分があるのかもしれませんね。 森鴎外の娘の話は面白かったです。2021/07/22
春埜秋岡
2
本書は、恋愛から離脱するという形の成長を遂げる女三の宮が、源氏という恋愛物語を揺るがせていると指摘する。これはある程度納得できる。だが三の宮の言葉が源氏の「光」性を排除するとあるのはよくわからなかった。2018/01/10
mirun
0
研究史上「内面」のない女君とされる女三宮の、「内面」とは、何故それがないとされたのかが多角的に考察されている。女三宮評については近年、従来研究よりも肯定的な評価がなされているように思うが、いずれも彼女の性愛を解しない人物像をある種幼いものとしてきた背景があるかと思われる。その点において女三宮を幼いと称するのはあくまで物語や読み手の論理であり、ないと言われている「内面」が存在しない人物ではないことを明らかにする点が良かった。研究による内面の評価が元来「近代的内面」によりがち、というのもかなり納得できる。2025/02/18