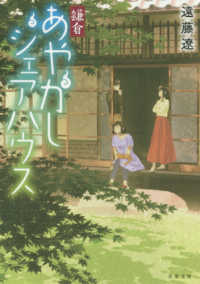内容説明
鎌倉初期に成立した説話文学『宇治拾遺物語』には、近代まで語りつがれた「昔話」とよく似た話がある。口承の昔話と説話文学を重ねて、浮かび上がってくる違い、つまりそれぞれの特質とは?共通する「話型」を軸に東アジアやヨーロッパにまで視界を広げ、『宇治拾遺物語』の読みが時空をまたぐ。
目次
1 昔話と『宇治拾遺物語』
2 瘤取爺
3 腰折雀
4 博徒婿入
5 藁しべ長者
6 猿神退治
7 『宇治拾遺物語』の説話と出典
まとめに
著者等紹介
廣田收[ヒロタオサム]
1949年大阪府豊中市生まれ。1973年3月同志社大学文学部国文学専攻卒業。1976年3月同志社大学大学院文学研究科国文学専攻修士課程修了。専攻、古代・中世の物語・説話の研究。学位、博士(国文学)。現職、同志社大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 王弟殿下のお茶くみ係【単話】 7 Re…
-

- 電子書籍
- 夜のベランダ【タテヨミ】第53話 pi…
-
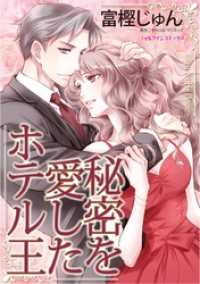
- 電子書籍
- 秘密を愛したホテル王【分冊】 9巻 ハ…
-
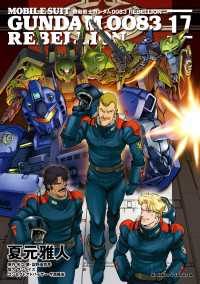
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム0083 REBELL…