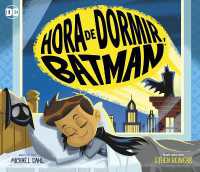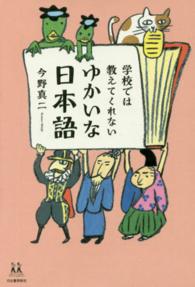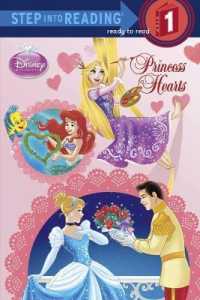出版社内容情報
《内容》 修の序
清野 弘明
太田西ノ内病院糖尿病センター設立時に運動療法指導室を併設し
たのが1975年,29年前のことであります.この時,日本体育大学卒
業後,高校の体育教師を志していた青年に,運動指導室の運動トレ
ーナーとしてぜひ勤務してほしいという依頼がありました.この依
頼の承諾から太田西ノ内病院・運動指導室が開設したことになりま
す.たった一人で始めた運動指導室に,現在は大学で運動生理学・
運動生化学を学んだ4人の運動トレーナーが勤務しています.
約30年,一貫して糖尿病の運動療法に携わり指導してきた藤沼宏
彰氏の実践運動療法のすべてがこの本に凝集されています.患者さ
んに,いかに楽しく運動療法を実践していただくか,そのためには
どういう運動指導が良いのかを試行錯誤してきた長い道のりが,随
所に見え隠れします.
健康行動理論を運動療法に取り入れた第1章は,運動療法の指導
を始めようと思っている糖尿病医療スタッフにとっても,運動療法
の指導に携わってきた方々にとっても参考になると思われます.患
者さんに「よし運動してみよう」と思っていただくためのノウハウ
が記載されています.
本書の圧巻は,ケース別運動指導と患者さんからのレポートです.
よく経験される症例の運動処方がきめ細かく記載されています.ま
た,患者さんのレポートは運動療法を実践・継続している患者さん
の生の声です.個々の患者さんへ運動トレーナーからの感謝の言葉
で締めくくっています.
実践的な運動療法指導のためには,どうしたら良いのかという視
点で書かれた本書が,運動療法指導者の一助になれば,われわれの
望外の幸せであります.
本書を出版するにあたり,われわれの無理なお願いを取り入れた
出版をお認めいただいた診断と治療社と編集に多大なご苦労をいた
だいた編集部の小池さつき女史に心から感謝いたします.さらに,
東北大学名誉教授後藤由夫先生に推薦の序をいただき,心より感謝
申しあげます.
最後に運動療法を立ち上げてくださった故阿部祐五先生,運動療
法に花を咲かせてくださった故阿部隆三先生に本書を捧げたいと思
います.
2004年3月
推薦の序
東北大学名誉教授・日本糖尿病協会名誉理事長
後藤 由夫
《目次》
監修の序………………………………………………………清野弘明
推薦の序………………………………………………………後藤由夫
はじめに………………………………………………………藤沼宏彰
1.運動をはじめていただくために
健康信念モデルを背景に
脅威を感じていただく
運動不足と糖尿病
運動不足は肥満の原因
運動不足と脂肪の蓄積
肥満の判定
肥満症の判定
肥満と生活習慣病
運動不足を認識していただく
運動量測定機器を用いる
生活習慣を振りかえる
運動不足と身体機能
運動に関係する器官
使わないための変化
体力の低下を知っていただく
平衡感覚
脚筋力
腹筋力
柔軟性
全身持久力
体力低下の重大性を認識していただく
運動の有益性を理解していただく
運動の急性効果
運動による血糖変動
柔軟性の改善
運動の爽快感(汗)
運動の慢性効果
糖代謝の改善
脂質代謝の改善
体型の改善
体力の改善
生活習慣病(糖尿病)の予防効果
関連疾患の予防と治療
運動を実施するうえでの障害が少ないと感じる
時間がとられる
細切れでも良い
生活活動を見直す
優先順位を高める
運動は辛い
勝つための運動とは違う
運動は快感(汗)
特別な準備が必要
特別な道具はいらない
普段着でもかまわない
自己効力を背景に
自己効力感を高めるために
自己の成功経験
日常行っている運動
昔行っていた運動
代理的経験
高齢者
肥満者
言語的説得
医療スタッフ
同病の仲間
生理的情動的状態
運動指導室の雰囲気
指導者の資質
運動の爽快感
2.運動を継続していただくために
情報の収集
メディカルチェック
血糖コントロール状態と運動
インスリン作用が不足し,血糖値が高いとき
インスリン作用が正常で,血糖値が低いとき
インスリン作用が過剰で,血糖値が低いとき
不安定型糖尿病
糖尿病合併症と運動
網膜症
腎 症
神経障害
その他の疾患と運動
関連疾患
循環器
運動器
フィジカルチェック
体 型
身長,体重,BMI
体脂肪
身体周径囲
体 力
筋 力
持久力
平衡感覚
柔軟性
敏捷性
ライフスタイルチェック
運動の実施状況
現在の運動実施状況
過去の運動経験
日常の活動量
仕 事
家 事
通勤,買い物
生活時間調査
平日の生活時間
休日の生活時間
個々に応じた運動指導
運動処方
運動種目
有酸素運動
身体の動きを良くする運動
筋力トレーニング
スポーツ
運動強度
酸素摂取量(V・O2)
心拍数
主観的運動強度(Rate of Perceived Exertion:RPE)
継続時間
一番良いのは
短くても
長くても
実施時間帯
一番良いのは
食後にできなければ
避けたほうが良いのは
実施頻度
一般的には
少なくても
毎日するなら
運動の効果を引き出すために
運動と休養
運動と栄養
運動のしすぎ
処方に従った運動ができない方へ
時間がとれない
通勤を見直す
買い物を見直す
仕事や家事を見直す
活動量の増加目標
趣味を生かす
身体に支障がある
悪くないところを中心に運動する
ぶらぶら歩きでも良い
ストレッチングだけでも良い
評価とフィードバック
目標の設定
中長期的ゴール
短期的ゴール
評 価
いつ評価するか
目標の修正
フィードバック
結果を示す
原因を探る
賞 賛
褒 賞
楽しく
3.運動指導の実際
ケース別運動指導
運動のきっかけと継続のささえ(体験者のレポート)
付 録
1.ライフスタイル調査票
2.さまざまな身体活動のエネルギー代謝率(METs)
3.ストレッチングの実際
4.筋力トレーニング
索 引
内容説明
本書の第1部では運動療法が必要な理由と有効性、第2部では運動継続が押しつけではなく自発的にやりたくなるように述べられている。第3部は体験談でこれだけ読んでもモチベーションを高められる。
目次
1 運動をはじめていただくために(健康信念モデルを背景に;自己効力を背景に)
2 運動を継続していただくために(情報の収集;個々に応じた運動指導)
3 運動指導の実際(ケース別運動指導;運動のきっかけと継続のささえ(体験者のレポート))
付録
著者等紹介
清野弘明[セイノヒロアキ]
1985年金沢大学医学部卒業。1988年東北大学医学部第3内科入局。1992年太田西ノ内病院糖尿病センター内科。1997年太田西ノ内病院糖尿病センター部長。2000年太田西ノ内病院糖尿病センター長。福島県立医科大学第3内科非常勤講師。2003年東北大学大学院分子代謝病態学糖尿病・代謝科臨床助教授
藤沼宏彰[フジヌマヒロアキ]
1974年日本体育大学卒業。(財)体力づくり指導協会入社。1975年太田綜合病院勤務。1979年東北大学医学部第3内科研究生。1987年医学博士学位取得。現在、太田西ノ内病院運動指導室長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
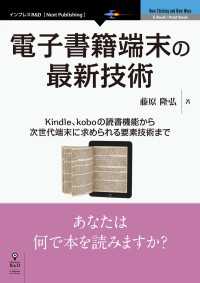
- 電子書籍
- 電子書籍端末の最新技術 - Kindl…