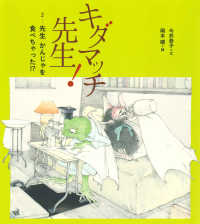- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学内科系
- > 周産期医学(新生児学)
出版社内容情報
《内容》 実地臨床の場で役立つよう基本的な考え方,臨床の場で行われている方法,チェックポイントを具体的に,医学生・コメディカル・新生児に携わる小児科医,産科医のために解説 《目次》 1 新生児ケア(多田 裕) 1.新生児医療の変遷 2.新生児集中治療室の概念 3.新生児集中治療室でのケア 4.これからの新生児ケア 2 新生児の生理的特徴(河野寿夫) 1.呼吸 a.呼吸器系の発達 b.ガス交換 1)胎盤におけるガス交換 2)第一呼吸 c.新生児の呼吸器系の特徴 1)呼吸数が多い 2)横隔膜優位の呼吸 3)胸壁が柔らかい 4)鼻呼吸 5)呼吸調節の未熟性 2.循環 a.胎児循環 b.新生児循環 3.黄疸 a.ビリルビンの代謝 1)ビリルビンの産生 2)ビリルビンと蛋白との結合 3)肝における代謝 b.新生児生理的黄疸と病的黄疸 4.消化 a.吸啜,嚥下の発達 b.消化・吸収の機能的発達 1)糖 2)蛋白 3)脂肪 5.水および電解質代謝 a.水 b.カルシウム,リン 6.腎臓 a.腎糸球体機能 b.尿細管機能 7.体温 a.熱の産生 b.熱の喪失 c.中性温度環境 8.免疫 9.血液 a.赤血球 b.白血球 c.血小板 d.凝固系 10.神経系 3 主要症状と処置(清水正樹/大野 勉) 1.チアノーゼ a.概念 新生児チアノーゼの生理的特徴 b.症候分類 1)中心性チアノーゼ 2)末梢性チアノーゼ c.診断と検査 d.処置 2.呼吸困難 a.概念 b.症候分類 1)多呼吸 2)陥没呼吸 3)呻吟 4)シーソー呼吸 5)鼻翼呼吸 c.診断と検査 d.処置 1)酸素投与 2)人工換気療法 3)アルカリ療法 3.無呼吸発作 a.概念 b.症候分類 1)中枢性無呼吸 2)閉塞性無呼吸 3)混合性無呼吸 c.診断と検査 d.治療 1)早期発見による蘇生 2)薬物療法 4.喘鳴 a.概念 b.症候分類 c.診断とその処置 1)後鼻腔閉鎖 2)喉頭軟化症 3)血管輪 4)気管軟化症 5)気管狭窄 6)その他 5.けいれん a.概念 b.症候分類 1)微細発作 2)間代性発作 3)強直性発作 4)ミオクローヌス発作 c.診断と検査 d.処置 1)一般的処置 2)原因疾患の治療 3)抗けいれん薬 4)その他 6.出血 a.概念 b.症状 c.おもな疾患とその処置 1)ビタミンK欠乏性出血 2)汎発性血管内血液凝固症 3)先天性凝固因子欠乏症 7.黄疸 a.概念 b.症候分類 1)生理的黄疸 2)母乳黄疸 3)病的黄疸 c.診断と検査 d.処置 1)光線療法 2)アルブミン補充療法 3)交換輸血 4)その他 8.嘔吐 a.概念 b.症候分類 c.診断と検査 d.処置 9.哺乳障害 a.概念 b.症候分類 c.診断と検査 1)哺乳障害と病因診断 2)哺乳機能の障害の評価 d.処置 1)基本的管理と介助 2)哺乳姿勢 3)栄養摂取法 4)過敏に対する訓練(脱感作) 10.腹部膨満 a.概念 b.症候分類 c.診断と検査 d.処置 11.発熱 a.概念 b.症候分類 c.診断と検査 d.処置 12.低体温 a.概念 b.症候分類 c.診断と検査 d.処置 e.寒冷障害 13.皮膚の異常と腫瘤 a.概念 b.症候分類と診断・処置 1)皮疹 2)血管腫 3)分娩外傷 4)中枢神経系奇形 4 新生児の疾患 1.呼吸器疾患(常石秀市/中村 肇) a.先天性呼吸器疾患 1)先天性嚢胞状腺腫様肺形成異常 2)気管食道瘻 3)肺低形成 4)先天性横隔膜ヘルニア b.後天性呼吸器疾患 1)呼吸窮迫症候群 2)胎便吸引症候群 3)新生児一過性多呼吸 4)エアーリーク 5)肺出血,出血性肺浮腫 c.慢性肺疾患 d.未熟児無呼吸発作 2.循環器疾患(常石秀市/中村 肇) a.機能的循環器疾患 1)心不全 2)未熟児動脈管開存症 3)新生児遷延性肺高血圧症 4)不整脈 b.器質的(先天性)循環器疾患 1)非チアノーゼ性心疾患 2)チアノーゼ性心疾患 3.感染症(常石秀市/中村 肇) a.経胎盤感染 1)トキソプラズマ症 2)風疹 3)サイトメガロウイルス感染症 4)梅毒 5)その他 b.経産道・経母乳感染 1)単純ヘルペスウイルス感染症 2)淋菌 3)クラミジア 4)B型肝炎ウイルス 5)成人T細胞白血病ウイルス 6)その他 c.院内感染 1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 2)緑膿菌感染症 d.肺炎・敗血症・髄膜炎 1)B群溶連菌感染症 4.黄疸を呈する疾患(米谷昌彦/中村 肇) a.生理的黄疸 b.新生児溶血性黄疸 1)血液型不適合による溶血性黄疸 2)その他の溶血性黄疸 c.母乳栄養に伴う黄疸 d.ビリルビン代謝異常症 e.新生児肝炎 f.胆道閉鎖症 g.鑑別診断 5.血液疾患(米谷昌彦/中村 肇) a.新生児多血症 b.未熟児貧血 c.新生児出血性疾患 1)ビタミンK欠乏出血症 2)潘種性血管内凝固症候群 6.中枢神経系疾患(高田 哲/中村 肇) a.低酸素性虚血性脳症(新生児仮死) b.頭蓋内出血 1)脳室内出血 2)硬膜下出血 3)くも膜下出血 c.脳室周囲白質軟化症 7.代謝性疾患(高田 哲/中村 肇) a.低血糖 b.先天性甲状腺機能低下症 c.先天性副腎皮質過形成 d.高アンモニア血症 8.消化器疾患(上谷良行/中村 肇) a.食道閉鎖 b.十二指腸閉鎖・狭窄 c.腸回転異常 d.鎖肛 e.ヒルシュスプルング病 f.肥厚性幽門狭窄症 9.泌尿器・性器疾患(上谷良行/中村 肇) a.先天性水腎症,閉鎖性尿路疾患 b.多嚢胞腎 c.尿道下裂 d.半陰陽 e.停留精巣 f.卵巣嚢腫 10.皮膚疾患(上谷良行/中村 肇) a.新生児中毒性紅斑 b.正中部母斑(サモンパッチ) c.単純性血管腫(ポートワイン血管腫) d.イチゴ状血管腫 e.蒙古斑・異所性蒙古斑 f.太田母斑 11.その他(上谷良行/中村 肇) a.口唇裂・口蓋裂 b.先天性内反足 c.先天性股関節脱臼 5 新生児養護の実際 5-1 分娩室における処置(本間洋子) 1.保温 2.気道吸引 1)注意点 3.臍帯結紮 4.新生児の蘇生 a.出生直後の評価と処置 1)アプガースコア 2)気管内挿管の実施要領 5.沐浴の可否 6.分娩室での児の評価 7.新生児治療施設への入院基準 5-2 正常新生児室におけるケア(渡辺とよ子) 1.新生児室における日常のケア a.新生児の保育環境 1)温度・湿度 2)感染予防 3)寝かせ方と乳幼児突然死症候群予防対策 b.新生児の日常のケア 1)生後12時間 2)授乳 3)医師による診察 4)看護婦による母児へのケア 2.新生児スクリーニング検査 a.正常新生児に必要な検査 1)黄疸の検査 2)血糖検査 3)C反応性蛋白 4)新生児メレナに関連する検査 b.マススクリーニング検査 1)対象疾患 2)新生児スクリーニングの有効性 3)実施方法 3.退院時指導 a.小児科医による新生児退院診察 1)哺乳と体重の変化 2)黄疸 3)臍帯の扱い 4)生後早期の呼吸障害やチアノーゼ 5)手術が必要な疾患を合併 b.看護婦による退院指導 1)退院指導の方法 2)退院時確認事項 5-3 NICUに収容すべき対象と新生児搬送(川上 義) 1.母体搬送と新生児搬送 2.NICUに収容すべき疾患 a.低出生体重児 b.早期産児 c.呼吸障害 d.チアノーゼ e.心雑音 f.新生児仮死 g.嘔吐 h.けいれん i.発熱 j.黄疸 k.奇形・odd-looking l.血便・吐血 3.新生児搬送の危険性 4.搬送の準備 a.人員 b.器具の準備 c.出発前の電話での指示 d.児の評価と安定化 e.清潔操作 f.気管内挿管・人工肺サーファクタント g.血糖の測定 h.胃管の挿入 i.輸液ルートの確保 j.家族への説明 5.搬送中の注意 a.体温管理(保温) b.呼吸管理 1)酸素投与 2)人工呼吸 c.観察 6.特殊な疾患の搬送中の管理 a.脊髄髄膜瘤 b.嘔吐を主訴の例 c.食道閉鎖 d.横隔膜ヘルニア e.臍帯ヘルニア,腹壁破裂 5-4 低出生体重児ケアの基本と実際 1.保温(小泉武宣) a.保温の重要性 b.保温における不利な生理学的特徴 c.中性温度環境と至適環境温度 d.保温の方法 1)保育器(閉鎖型保育器)の効果 2)ラジオアントウオーマー下(開放型保育器)の効果 e.低出生体重児の保温の実際 1)室内の温度と湿度 2)保育器 3)サーボコントロールかマニュアルか 4)カンガルーケア f.熱喪失の要因とそれに対する対策 1)輻射 2)対流 3)蒸発 4)伝導 2.呼吸管理(小泉武宣) a.肺の発達・成熟と出生時の適応 b.評価 c.処置 1)気道の確保 2)体温・循環の管理 3)酸素療法 4)器械を用いた呼吸管理 5)肺サーファクタント補充療法 3.循環管理(小泉武宣) a.胎児循環 b.新生児循環への適応 c.低出生体重児管理上の注意点 4.体液管理(杉山幹雄) a.低出生体重児の生理学的特徴と管理のポイント 1)体液量と体重減少 2)不感蒸泄と環境因子 3)電解質と腎機能 4)酸塩基平衡 5)糖 6)カルシウム b.輸液による体液管理の実際 5.栄養(杉山幹雄) a.目標と評価 b.低出生体重児の栄養 c.授乳の実際 d.静脈栄養 6.感染対策(藤生 徹) a.医療従事者の感染対策 1)入室時の注意 2)手洗い b.医療器具・機材に対する感染対策 c.感染症の早期発見 d.感染症児対策 7.黄疸(藤生 徹) a.高ビリルビン血症のリスクファクター b.血清総ビリルビン値のフォロー c.核黄疸危険増強因子 6 処置方法の実際 1.酸素療法(玉井 普/船戸正久) a.目的 b.方法 c.注意点 2.人工換気療法(玉井 普/船戸正久) a.適応 b.人工呼吸器の種類 1)間欠的強制換気 2)持続陽圧呼吸 3)自発呼吸同調型人工換気 4)吸気同調強制換気 5)圧支持換気 6)高頻度振動換気 c.人工換気療法の実際 d.人工換気療法の注意点 1)状態の急変 2)過剰な設定条件 3)合併症 3.モニタリング(和田 浩/船戸正久) a.心拍呼吸モニター 1)注意点 b.経皮酸素炭酸ガス分圧測定 1)注意点 c.パルスオキシメータ 4.血圧測定(和田 浩/船戸正久) a.観血的血圧測定 1)注意点 b.非観血的血圧測定 1)注意点 5.光線療法(船戸正久) a.目的 b.適応基準 c.光源の種類と照射方法 1)光源の種類 2)照射方法 d.施行上の注意点 1)性腺保護 2)両眼の被覆 3)照射距離 4)体温測定 5)輸液量 6)血清ビリルビン値の測定 7)他児への配慮 e.合併症 6.交換輸血(船戸正久) a.目的 b.適応 c.方法 d.使用する血液の選択 e.施行上の注意点 1)交換輸血総量 2)交換輸血の速度 3)クエン酸保存血の場合 4)ヘパリン新鮮血を使用した場合 5)留置カニューレ,接続チューブの点検 6)モニター監視 f.合併症 7.血管カニュレーション(土田晋也) a.末梢静脈カテーテル法 1)準備するもの 2)方法 b.中心静脈カテーテル法 1)準備するもの 2)方法 c.臍静脈カテーテル法 1)準備するもの 2)方法 d.末梢動脈カテーテル法 1)準備するもの 2)方法 e.臍帯動脈カテーテル法 1)準備するもの 2)方法 8.採血法(土田晋也) a.針滴下法(静脈血採血) b.足底採血(毛細管血採血) c.動脈穿刺法 1)準備するもの 2)方法 9.採尿法(大森意索) a.採尿袋による採尿 1)準備するもの 2)方法および手技 b.導尿による採尿 1)準備するもの 2)方法および手技 c.膀胱穿刺による採尿 1)準備するもの 2)方法および手技 10.腰椎穿刺(大森意索) 1)準備するもの 2)方法および手技 11.脳室穿刺(大森意索) 1)準備するもの 2)方法および手技 12.硬膜下穿刺(大森意索) 1)準備するもの 2)方法および手技 13.胸腔穿刺(渡辺とよ子) 1)準備する器具 2)方法 14.腹腔穿刺(渡辺とよ子) 1)準備する器具 2)方法 15.心嚢穿刺(渡辺とよ子) 1)準備するもの 2)穿刺部位と方法 16.超音波検査(橋本和広/長谷川久弥) a.超音波検査の実際 1)検査の準備 2)検査の実際 b.超音波検査の各論 1)頭部超音波検査 2)心臓超音波検査 3)腹部超音波検査 17.CTおよびMRI(橋本和広/長谷川久弥) a.検査に使用する鎮静薬 b.CT検査 18.MRI検査(橋本和広/長谷川久弥) 1)撮像条件 2)撮像法 3)MRIの特徴 4)頭部MRI検査の実際 5)脊髄MRI検査 7 新生児の薬物療法(側島久典) 1.新生児・未熟児の薬物代謝の特徴 a.体内へ吸収 b.体内分布 1)薬物と血漿蛋白との結合 c.薬物代謝 1)第1相 2)第2相 d.薬物排泄 1)肝胆道系からの排泄 2)腎からの排泄 e.薬物血中モニタリング 2.薬物療法の実際 a.薬剤承認問題 b.授乳中母親への投与上の注意 c.母乳移行について 8 新生児の栄養法(山内芳忠) 1.人工栄養 a.育児用調製粉乳 b.低出生体重児用調製粉乳 c.人工乳における今後の課題 2.母乳栄養 a.母乳の栄養学的利点 1)蛋白質 2)脂質 3)糖質 4)ミネラル 5)鉄 6)微量元素 7)ヌクレオチド 8)ビタミン類,抗酸化作用 b.母乳の免疫学的利点 1)液性成分 2)細胞成分 3.最近の話題 a.母乳中のNO b.ケトン体の役割 c.母乳由来のリンパ球 d.humane neonatal care initiative 4.母乳栄養の問題点 9 家族への対応(堀内 勁) 1.胎児新生児期の母子の発達 2.NICUにおける母子の接触 a.早産母子の親子関係の発達 b.出産時の対応 c.NICU入院中の母子接触 d.面会ノート e.タッチングと着衣の抱っこ f.カンガルーケア g.退院前の母子同室 h.母子の早期濃厚接触がもたらすもの 3.正常新生児の母子接触 a.早期母子接触 b.母子同室・異室 10 新生児の予後の追跡(三科 潤) 1.フォローアップの重要性 2.精神運動発達の評価方法 a.乳児期の精神運動発達評価 b.幼児期の精神運動発達評価 3.新生児疾患の予後 a.低出生体重児の予後 1)超低出生体重児の生存率の改善 2)超低出生体重児の長期予後 b.子宮内発育遅滞児の予後 c.慢性肺疾患児の予後 d.多胎児の予後 1)多胎児の死亡率 2)多胎児の神経学的障害 3)多胎における脳性麻痺の発症頻度 4)双胎と脳室周囲白質軟化症の発症 5)多胎特有の病態による児の予後 e.新生児仮死の予後 1)低酸素性脳症の重症度と予後 2)重症新生児仮死の神経学的障害の頻度 11 新生児の医療体制(多田 裕) 1.センター施設 2.センター施設整備による予後の改善 3.NICU病床数の不足 4.周産期医療のシステム化 5.施設間の連携 付-1 新生児に関する用語・定義・略語(千葉 力) 1.学会による勧告 a.低出生体重児 b.妊娠(在胎)期間の短い児 c.妊娠(在胎)期間に比較して出生体重が著しく軽い児 d.出生体重が重い児 e.その他の用語 2.新生児の日齢の表現 付-2 身体発育曲線(千葉 力)
内容説明
本書は、現在新生児医療の第一線で活躍中の経験豊かな執筆者が、新生児未熟児の医療とケアに必要な内容をわかりやすく解説したものである。
目次
新生児ケア
新生児の生理的特徴
主要症状と処置
新生児の疾患
新生児養護の実際
処置方法の実際
新生児の薬物療法
新生児の栄養法
家族への対応
新生児の予後の追跡〔ほか〕
著者等紹介
多田裕[タダヒロシ]
東邦大学医学部新生児学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。