出版社内容情報
東大寺大仏の鋳造に産出した銅が使われた長登銅山。山口県中央の山中にいまも奈良時代の露天掘跡と採掘坑が残り、山麓では製錬炉の跡が多数みつかり、製錬時にでる滓や銅生産の道具が出土した。800点余の木簡の解読とあわせて、律令国家による銅生産と流通の実態を解明する。
内容説明
東大寺大仏の鋳造に使われた銅を産出した長登銅山。山口県中央の山中にいまも奈良時代の露天掘跡と採掘坑が残り、山麓では製錬炉の跡が多数みつかり、製錬時にでる滓や銅生産の道具が出土した。八〇〇点余の木簡の解読とあわせて、律令国家による銅生産と流通の実態を解明する。
目次
第1章 大仏鋳造に使われた銅(大仏造立時の銅はどこから;「奈良登」の伝説とかすかな証拠)
第2章 どのように採鉱したのか(銅鉱床の生成;露天掘跡;採掘坑群;古代の採鉱技術)
第3章 どのように製錬したのか(選鉱とその道具;製錬作業場;古代の炉;粘土と木炭;大溝と排水溝)
第4章 木簡からみた生産の実状(長登銅山の役所は;採掘の実状;製錬の実状;流通・運搬の実践)
第5章 その後の長登銅山(その後の長登銅山;長登銅山の保存と活用)
著者等紹介
池田善文[イケダヨシフミ]
1948年、山口県生まれ。立正大学文学部史学科卒業。美祢市文化財保護課長、美祢市長登銅山文化交流館館長を経て、現在、美祢市教育委員会遺物整理作業員、日本鉱業史研究会理事、美東町文化研究会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
18
自然の鉱物から「資源」をとりだす、という広い意味での鉱山なら、弥生の辰砂とか縄文の黒曜石とか、もっと古い時代にいろいろと存在する。しかし「金属」という狭い(というかより一般的な)意味での「資源」に限定すれば、やはり最初は青銅の主成分となる銅を想定するべきであろう。銅鐸や銅矛に使われた銅は同位体分析によって大陸・半島起源だと考えられているし、義満や清盛の時代にも明から銅銭を輸入していた。しかし、その間の奈良時代には皇朝十二銭や奈良の大仏を国産の銅でつくっていたのだ。では、その銅はどこで採掘されていたのか?→2024/03/02
-
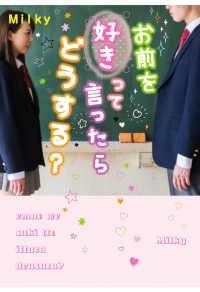
- 電子書籍
- お前を好きって言ったらどうする? スタ…







