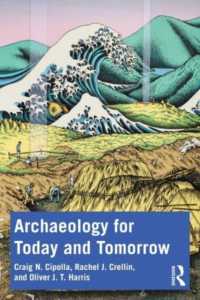出版社内容情報
東北新幹線や宇都宮・高崎線など北へむかう線路が集中する東京都北区の上中里で、四・五メートルもの厚みの貝塚がみつかった。しかも堆積しているのはマガキとハマグリの貝殻だけ。縄文人はなぜこの二種を営々と採取したのか、貝の身はどこへ運ばれ、誰が消費したのか。
内容説明
東北新幹線や宇都宮・高崎線など北へむかう線路が集中する東京都北区の上中里で、四・五メートルもの厚みの貝塚がみつかった。しかも堆積しているのはマガキとハマグリの貝殻だけ。縄文人はなぜこの二種を営々と採取したのか、貝の身はどこへ運ばれ、誰が消費したのか。
目次
第1章 姿をあらわした巨大貝塚
第2章 かきがら山の記憶
第3章 縄文時代の東京低地
第4章 巨大貝塚を解明する
第5章 縄文時代の水産加工場
第6章 内陸に運ばれた干し貝
著者等紹介
安武由利子[ヤスタケユリコ]
1982年、福岡県生まれ。東京学芸大学大学院教育学研究科修了。現在、北区飛鳥山博物館学芸員。さまざまなジャンルの展示会・講座などをおこなう一方、史跡中里貝塚の整備活用事業に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
15
規模的にも質的にも超ド級の貝塚が東京のど真ん中にあるのに、なぜか大森や加曽利に比べて知名度がいまひとつなのはなぜ? https://twitter.com/bamboo4031/status/16700106248842485772023/06/18
東堂秋月
3
マガキ、ハマグリの殻が大量に出土した貝塚遺跡。他の貝塚と異なり、土器などの生活臭のする出土品がほとんどなく、貝の種類も限られているので、縄文人が交易用に貝を計画的に採取して加工していた「海産物加工設備」だったとのこと。縄文時代は自給自足というイメージが強いけれど、そのような一般的な印象を覆す発見は「文字のない昔の人達も様々な工夫をして多様な生き方をしていたんだな」という実感が感じられて興味深い。中里産の干貝は縄文人に人気の名物ご当地グルメだったんだろうか。遺跡跡の公園も整備される計画があるらしく、期待大。2024/10/08