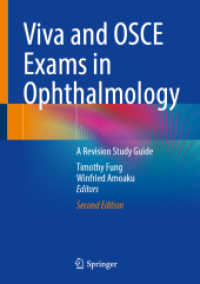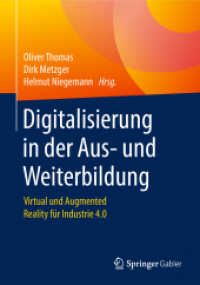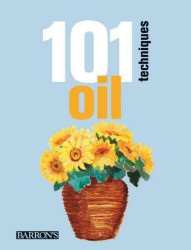内容説明
本書に登場する「やきもの」は大半が遺跡から出土したもので、接着剤でつないだり欠けた部分を石膏で埋めたりした、つぎはぎだらけのものが多いはずです。それらは実際に当時の日常生活を支えた道具で、中世社会の“生の実態”を伝えているのです。
目次
序章 中世考古学とやきもの
第1章 中世やきものの世界(やきものといえば椀と皿;中世やきものを代表するすり鉢 ほか)
第2章 中世やきものづくり(中世やきものの分類;さまざまな窯 ほか)
第3章 列島に広がるやきもの(列島に広がるやきもの;津々浦々のやきもの ほか)
終章 中世社会とやきもの(やきものと儀礼;食文化とやきもの ほか)
著者等紹介
浅野晴樹[アサノハルキ]
1954年、岐阜県中津川市生まれ。國學院大學文学部史学科卒業(考古学)。元埼玉県立さきたま史跡の博物館館長、元國學院大學兼任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
四不人
2
この種の本だと、様式の細かい差異や系譜の論考が続いて、そこに興味の無いものにはちょっと読みづらいものだ。が、この本はそこは軽く流して周辺の話題が多いので読みやすかった。やきものの本なのに「鉄」鍋とか漆器とか。欲を言えば、輸送の話をもう少し詳しく知りたかったが、とはいえ面白かった。2024/07/20
中村蓮
0
六古窯の特徴などといった個々の窯のやきものの特徴、中世国産陶器の特徴などや鑑賞の勘所を知りたかったのですが、やきものについてはあまり参考になりませんでした。しかし、遺跡から出土した土器から、中世の食文化、東西の差異の緩和など中世について新たな知見を得ることができました。2024/11/05