内容説明
いまもなお「人文知」は必要だ。新型コロナウイルスの感染拡大によってあらわになった民主主義の問題、分断や格差の問題。コロナの時代に本を読み、学び、社会について考えることの意味を、書店と教室の現場から問い直す往復書簡。文科系大学教師と書店店長との対話。
目次
はじめに 考える場所のために
1 書店論
エッセイ いまもなお本はライフラインだった
2 教室論
3 パンとサーカスと弁証法
エッセイ 「どうせやるなら派」から「コロナ転向派」へ、そして暴かれる五輪「ムラ」
4 言葉のパンデミックに抗うために
5 対談 書店と教室、人文知の現場から見えてきたこと
おわりに “未来の自分”と読書
ブックガイド 本書で取り上げた本やテクスト&パンデミックについてさらに考えるための五冊
著者等紹介
小笠原博毅[オガサワラヒロキ]
1968年生まれ。神戸大学大学院国際文化学研究科教授。ロンドン大学ゴールドスミス校社会学部博士課程修了。社会学Ph.D。スポーツやメディアにおける人種差別を主な研究テーマに据え、カルチュラル・スタディーズの視座から近代思想や現代文化を論じている。近年は、東京オリンピックや大阪万博の開催に一貫して異議を申し立て、批判を展開している
福嶋聡[フクシマアキラ]
1959年、兵庫県生まれ。ジュンク堂書店難波店店長。京都大学文学部哲学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sayan
27
書店でのトークイベントのごとく大学教員と書店店長の怒涛の往信・対談が進む。其々が立つ足元(=空間)を拠り所に、決して心地の良いものではない共生、とコロナと対峙していく姿勢を率直に批評し、コロナ禍を語り抽象論に終始する某コメンテーター(学者)をバッサリ切り捨てる。時々、勢いが止まらない書店店長の暴走に、教員が苦笑いと共に「頑固ですね」と合いの手を思わず入れる臨場感が良い。途中「(大学)授業ではオチは無く、常に不足と過剰が残る、それが魅力だ」と言い「遭遇」を補助線にコロナ前後の社会を語る視点は非常に興味深い。2021/04/07
ののまる
12
オンライン書店も利用するけれど、本屋は私にとって呼吸を整えて自分の立ち位置を再確認する場所。真剣に書店がどうあるべきかと取り組む店長さんがいることは心強い。書店が様々な人びとが行き交い集まる場所であるのに対し、ここでの大学は、あくまでも偏差値の高いエリート国公立大で、教師もひと昔の大学のようにかなりの自由度が確保されている、いまの大学現場では限定的な場所の話かなとも思う。2021/05/30
かんがく
11
副題にあるように「考える場所」、そして語る場所としての書店と教室が人文学の基盤となり、危機的状況にも対応しうるとの視点から、コロナ禍の現状を憂慮する書店員と大学教授の往復書簡。このまま書店が消え去ってしまうのはどうにか避けたいので、今日も書店に本を買いに行く。2021/07/28
チェアー
7
大学の教室での授業も、書店で本を選ぶことも、いずれもライブ感が重要な点で共通している。単に知識を得ることが大切なのではない。どんな過程で学んだか、本を選んだかが大切なのだ。ライブ感がなければ、教える側も本屋も、受け取り手からのフィードバックがないまま放置されてしまう。コロナ後に、ライブ感やリアル感について、多数派がどう考えるのか興味がある。多数派に与するものではないが。2021/02/05
ねこはひるね
7
語り合う言葉を存分に持つおふたりの往復書簡。弁証法、パンとサーカス、民主主義、知的で冷静なやり取りの中にも温度の高まりが感じられる。決して舞台には立たないけれど「いる」人の存在を当たり前に認めることが共生、と言う小笠原氏第七信、大声で発せられる言葉に支配されないよう、世界に豊穣な言葉があることに気づき、自らの欲望を言語化する、そのために書店空間があると言う福嶋氏第八信。パンデミックの渦中にのみこまれず生きるための言葉が力強い。 2021/02/10
-

- 電子書籍
- 2026-2027年合格目標 公務員試…
-

- 電子書籍
- これは二度目で最後の初恋【タテヨミ】3…
-

- 電子書籍
- 人気絶頂女優の私が、急死してぽっちゃり…
-
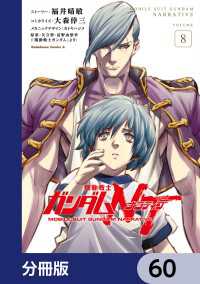
- 電子書籍
- 機動戦士ガンダムNT【分冊版】 60 …
-
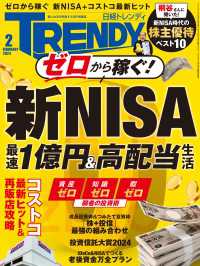
- 電子書籍
- 日経トレンディ 2024年2月号




