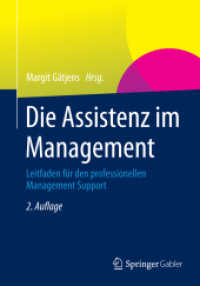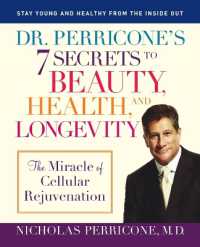内容説明
三重県松阪市の宝塚一号墳から全長一.四メートルもある巨大な船形埴輪が、当時のままに壮麗な姿をあらわした。大刀や蓋(きぬがさ)などで飾られた船、ともに出土した家形埴輪などは何を語っているのか。古代の人びとの死への恐れとその喪葬のあり方を埴輪群から解き明かす。
目次
第1章 船形埴輪からのメッセージ(日本最大の船形埴輪;さまざまな埴輪;土器と土製品;宝塚一号墳出土埴輪の位置づけ)
第2章 出島状施設をもつ古墳(発掘調査へ;確定された墳形;全貌をあらわす出島状施設;出島状施設の系譜)
第3章 喪葬次第を写す舞台(外界から閉ざされた埴輪群;囲形埴輪を読み解く;喪葬次第を写す舞台)
第4章 伊勢の王(宝塚一号墳出現前夜;宝塚古墳群を支えた集団;伊勢の王とその後継;倭王権の東方拡大;地域王権から倭王権の直接支配へ)
第5章 宝塚一号墳が語るもの
著者等紹介
穂積裕昌[ホズミヒロマサ]
1965年、三重県生まれ。同志社大学文学部文化学科(文化史学専攻)卒業。博士(文化史学)。三重県埋蔵文化財センター、三重県教育委員会で三重県内の発掘調査と文化財保護行政に従事し、現在、斎宮歴史博物館主幹(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
14
本居宣長や松浦武四郎の出身地ということで関心はあった。その上で、この宝塚古墳+船形埴輪と、雲出川流域の前方後方墳群の存在を知ったからには、松坂に絶対行かねばなるまい。。 それにしても鳥と船は、この時代の人間の「死」の観念にどうリンクしてたのか、、、。陸に縛りつけられている人間にとって、それぞれが空と海という「彼岸」に向かう存在の象徴だったのかもしれない。2021/07/23
もるーのれ
6
船形埴輪は、大きさも勿論のこと、威儀具による装飾も豊かで、王の魂を運ぶ船に相応しい。宝塚1号墳はこの他にも、出島状施設を持っていたり、湧水・導水施設を伴う囲形埴輪が出土していたりと、古墳の葬送儀礼を考える上で重要な資料である。導水施設の機能を亡き王の殯に伴うものとする考え方は興味深い。また、当古墳は当代の伊勢では最大級の前方後円墳で、海上交通を掌握していた王の存在が窺われるが、その後は倭王権の直轄になっていくというのも、この地の重要性を示している。2025/04/20