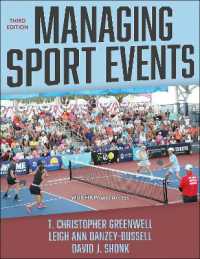内容説明
七世紀に天皇の宮が継続して営まれた飛鳥。のどかな田園風景の下にはタイムカプセルのように、宮殿の遺構が保存されている。斉明朝から天武・持統朝の宮殿遺構の解明によって、天皇と群臣の関係をみなおし律令体制を確立しようとした姿をみる。
目次
第1章 飛鳥宮の発掘
第2章 飛鳥岡本宮・飛鳥板蓋宮
第3章 後飛鳥岡本宮
第4章 飛鳥浄御原宮
第5章 文献史料からみた飛鳥宮
第6章 飛鳥から藤原へ
著者等紹介
鶴見泰寿[ツルミヤストシ]
1969年、名古屋市生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士課程前期課程史学地理学専攻日本史専門修了。現在、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館主任学芸員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
42
飛鳥時代の宮殿遺跡である「飛鳥京跡」は、古いものから順にⅠ期は舒明天皇の飛鳥岡本宮、Ⅱ期は皇極天皇の飛鳥板蓋宮、Ⅲ期は斉明天皇・天智天皇の後飛鳥岡本宮、天武天皇・持統天皇の飛鳥浄御原宮であることが確認されています。律令制国家と呼ばれる新しい国づりが行われた宮であり、その建物配置の変遷などに古代国家の形成過程が反映されている旨を述べた本です。学術的ですが、平易な文章で綴られており理解しやすい内容です。2019/12/01
翔亀
31
100巻を超えて刊行され続けているシリーズ「遺跡を学ぶ」。飛鳥へ万葉集の旅に行くなら、せっかくだから、とこれまであまり興味のなかった遺跡も見てみようかと、初めてこの種の本を手に取った。古墳となるとハードルが高かったろうが、これは宮廷という建物だから身近に感じられる。日本書紀に記された舒明天皇の飛鳥岡本宮と皇極天皇の板蓋宮と天武天皇の浄御原宮が、発掘により同じ場所に建てられていたことが分かり、その建物の配置と機能が明らかにされるさまはスリリングだ。2010年に平城京の内裏にあたる建物が発掘されるなど、↓ 2017/03/17
月をみるもの
15
考古学と文献学がオーバーラップし始める時期/場所としての飛鳥。日本書記は時代が遡れば遡るほど信用できないわけだが、この頃だとまだ書いてあること(建物の場所とか火災とか)と発掘される状況が一致する場合もそれなりにあるようだ。途中で大阪と滋賀に遷都したのは、やっぱり中国や韓国との関係が理由なんだろなあ。。。2019/04/29
chang_ume
10
ほぼ同一地点に重複するi期(舒明朝飛鳥岡本宮)、ii期(皇極朝飛鳥板蓋宮)、iii-A期(斉明朝後飛鳥岡本宮)、iii-B期(天武朝飛鳥浄御原宮)について、時期ごとの遺構特徴から律令国家成立期の宮都構造を理解していく。とりわけ史料に建物名称の記載が多い天武朝期に関して、エビノコ大殿を大極殿ではなく朝堂とする点(飛鳥宮大極殿非在説)、内郭北区画に南北に並ぶ大型建物を大安殿と内安殿とする点、官衙を北方の石神遺跡も含む分散配置とする点など、著者独自の解釈も紹介される。丁寧な解説と豊富な図版が大変参考になった。2022/07/16
take5
10
(他の方の感想で主なポイントは押さえられているので、その他に興味深かった点をいくつか)●明日香村を訪れると(私は3度訪れたことあり)、飛鳥寺の辺りから伝(でん)飛鳥板蓋宮跡の辺りまで田畑が広がっていますが、実は藤原京遷都時に飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)のほとんどが丁寧に解体され(柱の多くが再利用されたようです)てから、その上に土がかぶせられて、その後耕作地になったことと、昭和に制定された2つの特別措置法によって大規模開発を免れたことで石敷き舗装や建物の床下など遺構の残りが非常によかったそうです。2019/07/12
-

- DVD
- 多淫な人妻 ねっとり蜜月の夜