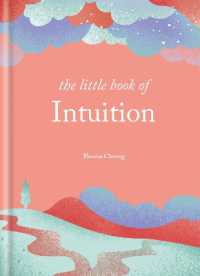内容説明
石器にはじまる道具と技術の進歩が、今日の高度な科学技術を生みだし、産業社会の繁栄をもたらしたが、道具を作るこころと使うこころがいつも正しくかみ合うような人類の英知こそが、確かな二十一世紀への展望をもつことにつながるものと信じて疑わない。
目次
1 道具のルーツ(人類が作った最初の道具―オノ;素材は道具のいのち―ナイフ;石片に隠された技術;一万年前の飛び道具―投槍;火の利用と土器の誕生;漁労を発展させた骨角器―釣り針;学ぶところのある縄文人の食文化;縄文人の精神生活―土偶;銅鐸の謎をめぐって;大きく変わる縄文人像;技術の進歩と人類の未来)
2 縄文土器の世界(土器はなにを語るか;縄文土器への憧憬―有孔鍔付土器;縄文人の心理の深層―抽象文装飾土器;縄文人のエネルギー―水煙土器;小さな器に豊かな祈り―吊手土器;縄文土器の美―顔面付吊手土器;縄文の八ヶ岳の世界―神像筒型土器)
著者等紹介
戸沢充則[トザワミツノリ]
1932年、長野県岡谷市に生まれる。1945年秋、旧制中学校一年生の時に、学校の裏山で縄文土器片を拾い歴史の真実に触れた感動から考古学の道を歩む。高校生時代には、藤森栄一氏が主宰する「諏訪考古学研究所」に参加。その後、明治大学文学部考古学専攻に進学。以後、明大で岩宿時代・縄文時代の研究と学生の指導をつづけ、明大考古学博物館長、文学部長、学長を歴任。2000年3月に退職。明治大学名誉教授。2012年4月9日、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。