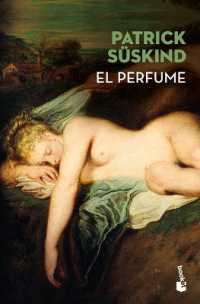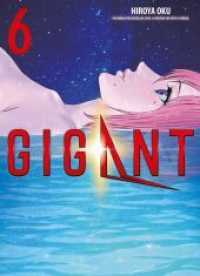内容説明
“天下つくらしし大神の御門ここに在り”。「出雲国風土記」は、雲南市・三刀屋の郷をして、こう記している。この「出雲王朝三刀屋説」をもとに、深遠なる古代出雲史を掘りおこし、鉄と農耕に生きた古代出雲族の世界を蘇らせる。
目次
1 故郷、出雲へ(砂の記憶;胸騒ぎ;出雲王朝;御門の里めぐり ほか)
2 再びの古代出雲(わが一族は鍛冶屋なり;御門と鉄の残映;みとやっ子;「出会いの里・御門火まつり」 ほか)
著者等紹介
石飛仁[イシトビジン]
本名・樋口仁一。1942年8月生まれ。島根県飯石郡三刀屋町・給下三刀屋一宮小学校出身・東京新宿区立富久小学校6年時に転校卒業。東戸山中学校(一期生)、駒沢大学高校から駒沢大学国文科卒業。劇団「青俳」演出部所属。劇団「現代人劇場」結成に参加。1970年退団後、ルポライター。1972年より光文社「女性自身」シリーズ人間班専属記者として30年間所属。ライフワーク「花岡事件」戦後未処理問題に取り組む。1984年から「事実の劇場・劇団不死鳥」を結成、演出・構成を手がける。現在、東京東アジア文化交流会代表、日本写真芸術専門学校講師、フリーライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
0
f181、サブタイトルに出てくる三刀屋というのは銅剣が358本出土し、かつて王宮の門もしくは宮殿があったと記述された土地(確かに大和政権に憚って単語を変えるって言われるとありそう)。銅鐸や銅矛がまとまって出た地点からも数キロ、著者さんはもともとの鍛冶の家系の子孫の方で、どうも戦時中の事件に関しての保証を行う段階で「記録は捩じ曲げられることがある」という決意を持って古代史に当たる決意を固めたのだとか、出雲の産鉄技術に関してを知りたかったんですが、これはこれで良かった、吉備との技術交流は少なくともあったのか。2015/07/29