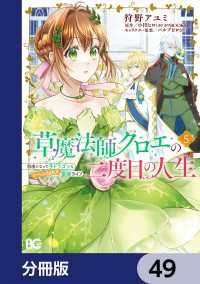内容説明
アンリ・ルフェーブルやミシェル・フーコーの議論を補助線にしながら、1990年代から現在までの再開発・住宅政策・郊外の変容やそれを支えるテクノロジーの特徴を検証し、流動性や利便性を求める空間の「不自由さ」と統治の関係性を分析する。
目次
序章 「空間の不自由」を問うということ
第1章 新自由主義と空間の暴力―金融資本と空間の接合
第2章 都市空間の変容のなかのオリンピック―再開発のなかの建築と空間
第3章 囲われる空間のパラドックス
第4章 スマートシティと生政治―パブリック.プライベートの産業から住むことの統治に向けて
第5章 郊外空間の反転した世界―『空中庭園』と住空間の経験
終章 新型コロナ禍と「ホーム」という場所―カフカ「巣穴」を読む
著者等紹介
佐幸信介[サコウシンスケ]
1966年、長野県生まれ。日本大学法学部教授。専攻は社会学、メディア論、住宅社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
awe
6
前提知識が不足しているのか、筆致があまりに晦渋なのか、高度に理論的なのか、とにかく読みづらく、筆者の問題意識は十分に理解できず、消化不良の感は否めない。門外漢を想定した本ではないのだろう。◆「住宅55年体制」なる言葉を初めて知った。「持ち家政策を軸にした住宅政策や住宅市場」(14p)であり、それは住宅を通じた景気浮揚策でもあったという。しかし90年代からその崩壊が始まる。住宅が金融商品としての性格を強める(金融市場と空間の接合)。「空間の動産化」「不動産の証券化」として表される諸現象は、公共空間の収縮を2023/08/12
Mealla0v0
4
90年代以降の空間の生産のモードが変化しているという。再開発、情報化、監視社会化、金融化。こうした変化は新自由主義的統治と歩を合わせている。再開発は、都市の公共空間を民営化し、空間を投資の対象へと変化させていく。再開発の主体は国家ではなく、新自由主義的政策は「開発を促す主体」として機能している。実際、再開発は民間企業主導による。東京湾岸エリアは高層化され、投資の容量を拡大させる。また、スマートシティは、地方自治体と企業による協働による、新たな統治モデルとして登場した。それはフローと人口を管理する統治術だ。2024/08/27
鵐窟庵
4
前半は近年の金融政策と都市再生の状況、市場ー制度の一体的な関係が生み出す、都市の起伏や格差に対する整理、問題提起や今後の動向、スマートシティやコミュニティ論へと展開。いずれの議論も誰が誰に/何に向かって、これから都市をどう作るか、の視座が通底している。その中枢に建築家の不在。三章末でコミュニティのセキュリティについて「自由な空間」を目的とするほど、「空間の自由」が失われていく、それを失わないために安全安心の負担を軽くしていく空間の作る方に新たな自由の可能性を感じる、という論点が制度論的にも新鮮だった。2021/10/04
Go Extreme
2
「空間の不自由」を問うということ 新自由主義と空間の暴力―金融資本と空間の接合: 都市空間の変貌 空間開発と金融資本 公共空間の市場化と社会的所有の放棄 都市空間の変容のなかのオリンピック―再開発のなかの建築と空間 囲われる空間のパラドックス: 集住空間のセキュリティ 象徴暴力とコミュニティ 逆説的な安全な空間 スマートシティと生政治―パブリック―プライベートの産業から住むことの統治に向けて 郊外空間の反転した世界―『空中庭園』と住空間の経験 新型コロナ禍と「ホーム」という場所―カフカ「巣穴」を読む2021/11/02