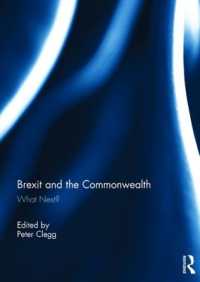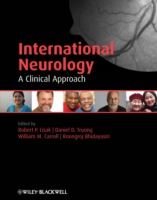- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
売り上げ減少や書籍のデジタル化など、いま、「本の世界」はグローバルに激動している!変化のときこそ若い力が必要だし、活躍できる。小学館での38年の経験をもとに、本作りの実態、編集技術、人脈の作り方、電子編集に必要な技、企画の立て方、などを具体的にレクチャー。大学での講義内容も盛り込んだ21世紀の「実戦の武器」!
目次
序章 編集者の一日―「本」って何だろう?編集って何をやること?
第1章 「本」の現場から
第2章 「本」はモノである
第3章 人脈こそ、編集者の「財産」
第4章 変化する編集の仕事
第5章 編集のキモは企画だ!
著者等紹介
大沢昇[オオサワノボル]
1952年、東京都生まれ。1974‐75年、シンガポールに在住してPANA通信に勤務、76年、東京外国語大学外国語学部中国語学科を卒業。小学館に入社し「週刊ポスト」編集部や外国語編集部などで働く。2013年に退社。現在は、大正大学客員教授、獨協大学講師、中国分析・総合センター代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kubottar
9
漫画「編集王」が好きなら読んだほうがいい。個人的には編集者はまだまだ必要な職業だと思います。本造りはどういうものなのかが少しわかった気がする。2014/07/22
あやかしゃん
1
授業レポートのために。編集者の仕事内容、"これからの"編集者に必要なことがとてもわかりやすく書かれている。若手編集者として先輩の意見やアドバイスを聞いているような気分で読んだ。紙の本はやはりこれからどんどん厳しい時代に突入するのだろうが、多方面のメディアに目を向けて発展させていく力があれば、編集者はまだまだ文化の重要な担い手だと感じた。2014/11/29
huyukiitoichi
1
今の時代編集者になりたいって人はどれぐらいいるもんかね。就活する時一瞬考えたけど30年後に職業として残ってなさそうだったので最初から除外してしまったことを思い出した。2014/07/01
悠々
0
★★★☆☆2016/09/10
トキ
0
編集の仕事だけでなく、造本や電子出版に関することまで懇切丁寧に解説した本。編集者になるには若いうちからその道に入って、人脈やスキルを培っていくことが必要で・・・。中途から入るのはかなり厳しそう。今でもじゅうぶん本の街のイメージがある神保町、昔とはそんな違いがあるのか、というのも分かって面白かった。2014/08/17


![Easy Languageプログラミング入門 - トレードステーションで実現!理想の株式投資ツールを [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866362480.jpg)