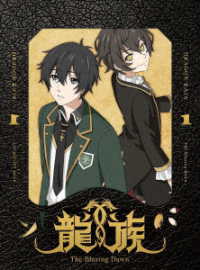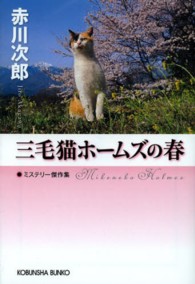出版社内容情報
民主主義社会を維持するためには、知る自由、学習する権利が絶対的な基盤である。そのデモクラシーを支えるのが図書館だ。とくに公共図書館は、市民にもっとも身近な教育施設として、書物や資料、情報を集積し、著者それぞれの知的営為を持ち寄った場である。
多くの人々の興味・関心を「持ち寄り」、利用者は世界中の本から自身の気づきを「見つけ」、わかる喜びをほかの人と「分け合う」。図書館は市民の〈知りたい〉を支え、情報のナビゲートを通じて主体性の確立を促す。そして、地域の情報ネットワークの中心となって人々に等しく寄り添い、まちの連帯と文化的な発展に寄与していく。まちの活性化の鍵は図書館にあるのだ。
構想段階から市民が参加して新しく作り上げた瀬戸内市民図書館は、2017年に「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」の大賞に輝く。その館長として図書館と地域の発展に貢献した著者が、自身の図書館員としての体験談を交えながら、地域の住民一人ひとりが主役になって作る現代の公共図書館像を描き出す。
目次
第1章 図書館を知っていますか?
第2章 文化としての図書館
第3章 持ち寄り・見つけ・分け合う広場を作る―瀬戸内市の図書館づくり
第4章 図書館とまち育て
第5章 図書館と蔵書づくり
第6章 図書館とデモクラシー
著者等紹介
嶋田学[シマダマナブ]
1963年、大阪府生まれ。奈良大学文学部教授。専攻は図書館情報学、公共政策論。大阪府豊中市立図書館や滋賀県永源寺町立図書館、滋賀県東近江市立図書館、岡山県瀬戸内市新図書館開設準備室長を経て瀬戸内市民図書館館長。2019年から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ででんでん
鳩羽
Bridge
yomite
akaneirosora
-

- 電子書籍
- 週刊SPA! 2015/4/14・21…
-

- 電子書籍
- エリートの創造和田秀樹の「競争的」教育論