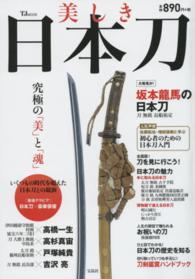- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
目次
蒲原有明(蒲原有明詩抄;ロセッティ訳詩より;飛雲抄より)
薄田泣菫(薄田泣菫詩抄;大国主命と葉巻;森林太郎氏;お姫様の御本復;鵞鳥と鰻;茶話より;艸木虫魚より)
著者等紹介
蒲原有明[カンバラアリアケ]
明治9年、東京に生れる。小学生の頃すでに文学書に関心し、第一高等学校に不合格となって入会した国民英学会で英文学に親しむなかで詩を作り始め、明治27年にはじめて作品を発表してから、一時期は小説、紀行で文名を知られるが、再び詩作に向い、ロセッティの影響下に抒情詩人として出立した。同35年の処女詩集「草わかば」に続く「独絃哀歌」以降、ヴェルレーヌあるいはブレイクの訳詩を交えつつ、それらの西欧の詩の精神と方法を日本語に移し入れることにつとめた成果は、同41年の「有明集」に示されるところで、一巻によって、日本の近代詩の先駆者の栄誉を「白羊宮」における薄田泣菫と並んで担う。昭和27年歿
薄田泣菫[ススキダキュウキン]
明治10年、岡山県に生れる。中学校を中退し、殆ど独学で和漢書、欧米の文学書を渉猟しては詩作をこととするようになるうち、ソネットを日本に移植する試みで認められた後、「絶句」と名づけたそれらを含む第一詩集「暮笛集」を明治32年に刊行、一連の浪漫詩のその新風は時代の青春に大いに迎えられ、やがて長詩「公孫樹下にたちて」を発表の頃には擢んでた地位を詩壇に占める。同39年の詩集「白羊宮」は、象徴詩風の文語定型詩の一達成を示して、集中の「ああ大和にしあらしかば」「望郷の歌」などの名篇は特にまた知られたが、この前後から詩作を廃するに近く、その後は「茶話」「艸木虫魚」他の随筆に才を揮った。昭和20年歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。