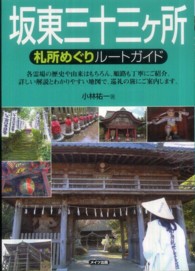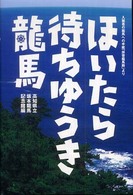- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
目次
徳富蘇峰(嗟呼国民之友生れたり;『透谷全集』を読む;還暦を迎ふる一新聞記者の回顧;紫式部と清少納言;淡窓全集;世界三文豪の満一百年忌;敗戦学校;宮崎兄弟の思ひ出)
黒岩涙香(『一年有半』を読む;藤村操の死に就て;朝報は戦ひを好む乎;小野小町論)
著者等紹介
徳富蘇峰[トクトミソホウ]
文久3年、水俣の郷士の家に生れる。熊本洋学校、同志社に学んでから、郷里で私塾大江義塾を経営する間に刊行の「将来之日本」で文名を知られ、やがて塾を閉じると上京し、明治20年民友社を設立して「国民之友」を発刊、同23年「国民新聞」を創刊する。新時代を平民の社会と位置づけた当初の論調が、日清、日露の両戦役を経て国家を重しとする色合いを濃くするのは、近代日本の困難な歩みを体現したものというべく、以降その姿勢を貫くまま敗戦に至るなかで昭和18年に文化勲章を受章。畢生の大著に大正7年に執筆を開始した「近世日本国民史」があり、戦犯として処遇された戦後も稿を継ぎ、昭和27年に全百巻を脱稿後、同32年歿
黒岩涙香[クロイワルイコウ]
文久2年、土佐に生れる。大阪英語学校に学び、海外の小説、それも主に探偵小説の翻訳を、明治20年の頃から諸新聞のみならず、自ら朝報社を興して発刊した「万朝報」に連載して一世を風靡する。その一方、同35年、社会主義を追求する理想的団結として、内村鑑三、幸徳秋水らと理想団を結成するが、日露開戦をめぐり、非戦論を唱える内村らと袂を分った。その後も大正の政局に絡みつつ、時務的な論説に筆を揮っては、「万朝報」に掲げる三面記事でも名を売ったが、文章を草して及ばざるところない趣で、明治の青年の間に迎えられた「天人論」があり、大正2年刊行の「小野小町論」は、卓れた批評として夙に一部に知られた。大正9年に歿する
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。