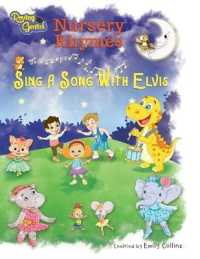- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
内容説明
日本文芸の歴史を考えるうえで、保田にとって後鳥羽院は動かしがたい核に位置する最重要の詩人だった。学生時代、芭蕉に教えられ、承久懐古の情に促されるまま隠岐島を旅して以来、数年にわたって書きためていた祈念の文章を『後鳥羽院』と題して上梓したのは昭和十四年、後鳥羽院七百年祭の歳にあたっていた。その三年後に三篇の新稿を加えた増補新版(本文庫)が刊行されている。本書は、「英雄と詩人」という著者年来のテーマに従って、文化擁護者としての後鳥羽院の志と事業を欽仰し、院に発し西行から芭蕉へと受け継がれる隠退者の文芸と美観に日本文学の源流と伝統を見出そうとした文学史の試みである。
目次
日本文芸の伝統を愛しむ
物語と歌
宮廷の詩心
桃山時代の詩人たち
後水尾院の御集
近世の唯美主義
芭蕉の新しい生命
近世の発想について
蕪村の位置
近代文芸の誕生
承久拾遺
契冲と芭蕉
国学の源流
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
13
日本文芸の歴史を考えるうえで、保田にとって後鳥羽院は動かしがたい核に位置する最重要の詩人だった。本書は、「英雄と詩人」という著者年来のテーマに従って、文化擁護者としての後鳥羽院の志と事業を欽仰し、院に発し西行から芭蕉へと受け継がれる隠退者の文芸と美観に日本文学の源流と伝統を見出そうとした文学史の試みである。 (カバーより)2014/03/31
depthofthesky
1
保田の文体に慣れるまでタイヘン。慣れると滋味深い。「憂結の歌」と「心ばへの歌」、芭蕉と後鳥羽院の関係など。 #dokusyo2010/03/22
-
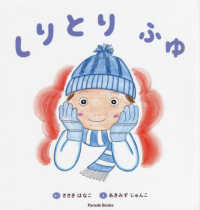
- 和書
- しりとり ふゆ
-
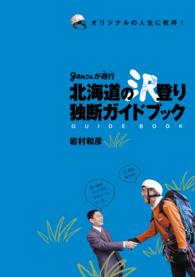
- 電子書籍
- 北海道の沢登り独断ガイドブック【HOP…