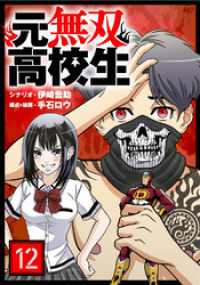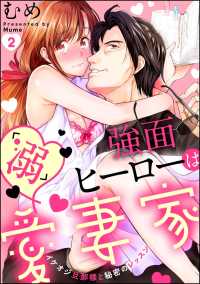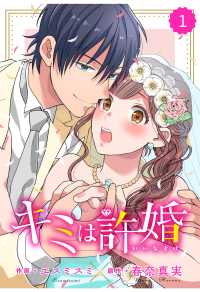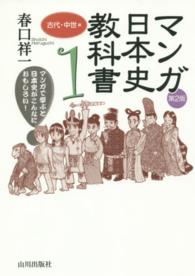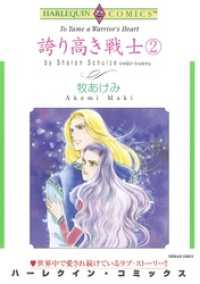- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
内容説明
昭和13年9月に刊行され、第2回透谷文学賞を受けた本書は、『日本の橋』『英雄と詩人』の2年後に出た3冊目の評論集である。収録作10篇は概ね昭和10年から13年にかけて発表されたものだが、最も早く書かれた「当麻曼荼羅」は昭和8年の発表になる。因みにこの作は、折口信夫の『死者の書』執筆のきかっかけになった。前二著が近代と西洋を媒介として文学的な拠点と感性を自ら語るエッセイが多かったのに比して、本書は日本の古典の美と信実を確信する文章を専らとし、世界史の中の「日本」を強く意識する保田29歳の決意とともに上梓された事情は「緒言」にみられる通りである。就中、神人分離を背景に、詩人と武人を一身に体現した悲劇的存在としての日本武尊を描いた表題作と、巻末に置かれた「明治の精神」は雑誌発表当時、文壇を刺戟した作である。
目次
戴冠詩人の御一人者
大津皇子の像
白鳳天平の精神
当麻曼荼羅
斎宮の琴の歌
雲中供養仏
更級日記
建部綾足
饗宴の芸術と雑遊の芸術
明治の精神
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
10
「齋宮の琴の歌」、「更級日記」が好き。岡倉天心と内村鑑三を軸に論じた「明治の精神」は時間を空けてもう一度読みたいと思います。2014/03/29
雁林院溟齋居士(雁林)
0
保田與重郎初期の論集。日本武尊を論じた表題作を初め、大津皇子、天平白鳳文化、更級日記、齋宮女御、建部綾足、そして岡倉天心と内村鑑三を中心にした「明治の精神」を、著者一流の「日本ロマン主義」とも言うべき立場から縦横無尽に論じている。「饗宴の芸術」と「雑遊の芸術」を初めとして一つ一つの論点が非常に面白いが、ピュシス的な日本の上代の「自然」とその「順序」、既に分からぬ内に喪失してしまった同殿共床への飽くなき回想は矢張り保田の精神を深く通底するものであり、明治の精神を論ずる際にも次元を落として似た構図を感じる。2013/04/28