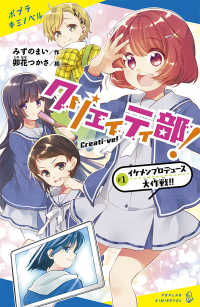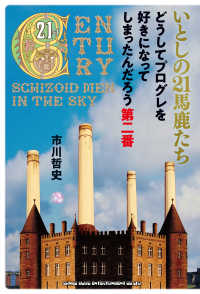内容説明
本作は巻末の落款によれば王鐸が自作の七言律詩40首を弟の子陶に書き与えたものである。年記の庚寅は清の順治7年(1650)、王鐸59歳になる。この年の作品は他に数種あり、その書風は、動きの大きな、迫力のある自由奔放な書き振りであるが、本巻は、弟に与えるという心のゆとりからか、非常に気楽に、気負わずに書いており、味わいの深い作品である。巻末には楷書の自跋が記されている。王鐸は行草書において有名であるが、小楷もまた、見事なものであり、僅か3行の、この書を見ても窺い知ることが出来る。この跋文が書かれたのは壬辰の年である。これは本文を書いた2年後、順治9年(1652)、王鐸61歳の時になり、この年の3月に王鐸は没しており、この跋文は晩年の書になる。王鐸の作品(題跋、詩稿等)数多くあるが、最晩年の順治9年の筆蹟は、寡聞にして、この跋文しか見たことがなく、貴重な資料である。尚、落款では七言律詩40首となっているが、書かれているのは七言絶句であり、書き誤ったのであろうか。