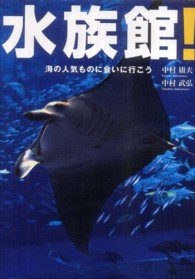- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
目次
第1部 若き日の前川恒雄―三〇歳前までの歩み(子どもの頃から中学生まで―朝鮮で;小松中学校、第四高等学校、金沢大学―引き揚げのあと;図書館員を目指して、図書館職員養成所で;小松市立図書館へ ほか)
第2部 前川恒雄と滋賀県立図書館(県政に文化の屋根をかける―武村知事の文化政策と図書館;前川恒雄滋賀県へ―三顧の礼;日野市助役・部長時代の経験;新県立図書館のスタート ほか)
著者等紹介
田井郁久雄[タイカクオ]
1943年生。東京教育大学卒。岡山市立図書館に30年勤務。就実大学、ノートルダム清心女子大学、岡山大学、阪南大学で非常勤講師。広島女学院大学准教授、2014年退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
14
1980年に前川さんが滋賀県立図書館の館長に就任されてから、それまで図書館後進県だった滋賀県が年間貸し出し冊数全国第一の図書館王国となった。前川さんの功績は大きい。本書で全盛期の頃の前川さんの活躍ぶりを知ることができた。しかしそれから約40年たった現在では図書館王国に陰りがみられる。ピークで1億6000万円以上あった県立図書館の資料費が嘉田知事の時代には6000万円を切るところまで落ち込んでいたとは知らなかった。滋賀県民として図書館にもっと目を向けていきたいと思う。2018/06/26
yyrn
8
日々、図書館にお世話になっていながら、運営の苦労には思い至らなかった。新聞の書評欄に載った新刊本はあって当たり前、予約が多いと不満が口に出る身勝手な利用者だが、この本を読むと、共に作り上げていくことの大切さを教えられた。いくら立派な施設があって、たくさんの蔵書があっても、利用を促す仕掛けがなければ、またそれに応える良い読み手がいなければ宝の持ち腐れとなり、利用率も下がって予算も削られていく・・・。ベストセラーばかりを一度に十何冊も購入して貸し出すのはいかがなものか。翌年には誰も借りない本がたくさんある。2018/08/18
sgwk農園牧場(前川)
2
明晰に考え、わかりやすく表現すること。 公共サービスのあり方は結局、職員の質によって決定されてしまうもの。図書館は人。図書館に限らず、人が人のために何かを成すということが大事だと感じさせられました。2022/11/28
必殺!パート仕事人
1
大島氏とはまた違う図書館員物語。前川さんが工学部出身だったとは。なので感情によらず理論的に利用者に役立つ図書館を作っていけたと。人材の養成は採用時から始まるのに、当時は館長の考えで適当に採用してたとか。80年代もそうでしたよ。開館時間を増やしても利用者が増えないのは、その館の居心地の良さによるのではないかと。つまりは職員の意識の高さによるのでは?読書にかかわる運動の変遷や日本図書館協会の変遷を分析しているのが興味深いです。作為した数値を全国図書館統計用に報告している館もあったそうで、なんじゃそりゃですよ。2023/11/25
とろる
0
小さな頃から県立図書館含め、県内の図書館にはお世話になったが、この本を読みおわり、滋賀県がいかに図書館に恵まれた県だったのかを今さらながら初めて知った。確かに、大きくなってから大阪府立や京都府立の図書館に行った時に、都会のくせにこんなにチープな図書館なのかと落胆した思い出もある。今もこうして読書をする習慣があるのは、前川さんのおかげなのかもしれない。ちなみに、この本に出会ったのも、やはり図書館だ。2018/05/20
-
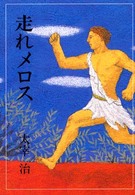
- 和書
- 走れメロス 偕成社文庫