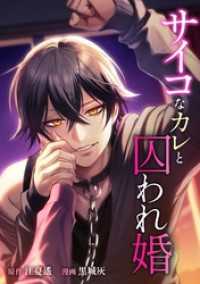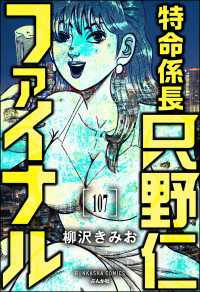- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
新宿の街から「広場」が消えた1969年から72年まで「誌上広場」をめざして、若者に圧倒的な支持を得て発行された伝説のタウン誌・元編集長がコラージュの手法で描く、この時代と時代の表現者たちの群像。
目次
第1章 その頃、新宿は「塹壕」だった
第2章 六〇年代から始まる自画像
第3章 アナーキーな風に吹かれて
第4章 焼け跡闇市派精神、ふたたび
第5章 コマーシャルの台頭、その光と影
第6章 「新宿砂漠」の井戸掘り人
第7章 七〇年代を生き抜くための航海談論
第8章 『新宿プレイマップ』の同志たち
第9章 タウン・オデュッセウスの旅立ち
著者等紹介
本間健彦[ホンマタケヒコ]
1940年、中国東北部(旧満州)生まれ。エディターズスタジオ「街から舎」主宰・ライター。『話の特集』編集者を経て、『新宿プレイマップ』編集長(1969~1972年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kokada_jnet
29
「伝説の雑誌」として知られている雑誌を編集長が回顧した本。スポンサーから期待される商店街のPR誌としての役割と、編集サイドがやりたいカウンターカルチャー雑誌としての路線で、ずっと苦悩していた感じ。2020/03/30
長老みさわ/dutch
3
サブタイトルにある通りタウン誌『新宿プレイマップ』の元編集長が記した「極私的フィールドノート」 69年7月から72年6月まで、文字通り「新宿の青春時代」に《新都心新宿PR委員会》のより、「副都心」ではなく「新都心」新宿のPRのためという名目のもとに恐らく初めての「タウン誌」として刊行された「新宿プレイマップ」の編集を中心に60年代後半から70年代初めまでの新宿と当時の「トンガッていた」アートクリエイター達を描いた一冊。 当時のカウンターカルチャーの状況がいきいきと描かれている。 2013/10/13
ざび
2
60年代とはいいつつ、タウン誌「新宿プレイ・マップ」が刊行されていた1969年から72年が中心となる。私にとっては同時代性はないが、高校以降知り得た、当時のカリスマの名前が踊っている。矢崎泰久、野坂昭如、殿山泰司、草森紳一、山下勇三、横尾忠則etc.伝説の新宿西口広場事件以降のめまぐるしく変化している時代の雰囲気が感じられます。2013/07/27
晴
1
当時、新都心として開発が進む新宿に迎合せず、戦後から1960年代末までの、攻め続けた新宿の姿勢を最後まで引き継いだタウン誌「新宿プレイマップ」。その在り方は本来のタウン誌とは真逆で、三年近くも永らえたのが不思議なくらいだけれど、「新宿」という街だからこそ成立しえたタウン誌とも言えて、その面白さがよくわかる内容だった。これまでは、私の中で「日本語ロック論争」についての文章を読むと必ず出てくる雑誌でなんだか得体のしれない存在だったけれど、読み終えた今はしっかりとした輪郭を持つ存在となりました。2017/05/23
hiratax
1
「新宿プレイマップ」はタウン誌だが、多くの文化人が集うごった煮雑誌だった。豪華なミニコミにも見える。街の細部をすくい上げる、空気を吸い込むような手法は雑誌の理念として潔い。リクルートの「ホットペッパー」「タウンワーク」なんかは、このあたりの地域ミニコミの手法をパクって、毒気を抜いて標準化した形態ではないかと。当事者に寄る回顧録だが当時の編集部員の行方が知れないというのも、雑誌のたたずまいを現しているようで良い。集合離散。2013/09/21