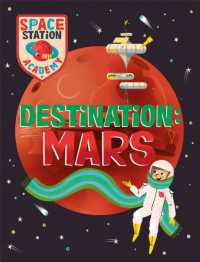目次
序 漱石文学の水脈
1 “漱石”への水脈―その摂取と受容(「死んでも自分はある」か―ジェイムズ、フェヒナー、ベルクソンと漱石;『倫敦塔』の視覚芸術的手法;若き漱石の英国「自然詩」研究;夏目漱石の英詩;研究コラム 漱石漢詩注釈拾遺)
2 “漱石”からの水脈―その影響と照応(「時」の力にあらがう「文学」―豊子〓(がい)『縁縁堂続筆』と夏目漱石『硝子戸の中』
“散文”と“詩”の出会うところ―夏目漱石と萩原朔太郎
漱石と芥川―特にハーン、アナトール・フランス、メリメとの関連において
独訳『三四郎』の基礎的研究―日本文化の翻訳をめぐって
研究コラム 書物としてのミュージアム―「夏目漱石内坪井旧居」の時空を考える)
著者等紹介
坂元昌樹[サカモトマサキ]
1968年生。東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程単位取得退学。熊本大学文学部准教授
田中雄次[タナカユウジ]
1943年生まれ。熊本大学名誉教授、日本映画学会常任理事長
西槇偉[ニシマキイサム]
1966年生。東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化専攻博士課程修了。熊本大学文学部准教授
福澤清[フクザワキヨシ]
1951年生。筑波大学大学院文芸・言語研究科博士課程単位取得退学。熊本大学文学部文学科超域言語文学コース教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。