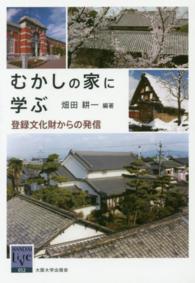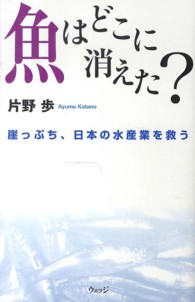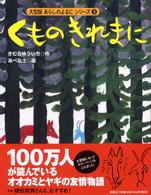出版社内容情報
50年代から60年代にかけて、戦後的な社会や政治の枠組み、党派的な文化への拠り所が失われ、言語そのものに依拠する<ことばが語る時代>が始まる。飯島耕一、大岡信ら、戦後詩から離陸する詩人たちと、天沢退二郎、吉増剛造ら、60年代とそれ以降の詩を担った詩人たちについての論が激しく踵を接する。
(月報=福間健二、岸田将幸ほか)
北川透[キタガワトオル]
著・文・その他
内容説明
五〇年代から六〇年代にかけて、戦後的な社会の枠組み、党派的な文化への拠り所が失われ、言語そのものに依拠する“ことばが語る時代”が始まる。前時代からの継続を暴力的に切断した「凶区」などの言語の断層、急勾配、崩落の現場に、詩の危機と転生を読みとる巻頭論考のほか、飯島耕一、大岡信、入沢康夫ら、戦後詩から離陸する詩人たちと、鈴木志郎康、天沢退二郎、吉増剛造、佐々木幹郎ら、六〇年代とそれ以降の詩を担った詩人たちについての論が激しく踵を接する。
目次
1 詩的断層十二、プラス一―“六〇年代詩”経験の解体・私論(断層十二;プラス一)
2 戦後詩からの離陸(飯島耕一論;大岡信論;入沢康夫論―匿されているものの痛い破片 ほか)
3 六〇年代詩とその行方(鈴木志郎康論;菅谷規矩雄論;天沢退二郎論 ほか)
著者等紹介
北川透[キタガワトオル]
1935年、愛知県碧南市に生まれる。58年、愛知学芸大学卒業。62年、「あんかるわ」を創刊し、90年に終刊するまで、同誌を基盤に精力的な詩と批評の活動を展開する。91年、下関市に移住し、96年から2000年まで、「九」を山本哲也氏と共同編集で刊行。2013年から、ひとり雑誌「KYO(峡)」刊行。『詩論の現在』(全三巻)で第三回小野十三郎賞、詩集『溶ける、目覚まし時計』で第三十八回高見順賞、『中原中也論集成』で第四十六回藤村記念歴程賞、これまでの詩の実践と現代詩論への寄与で第七十回中日文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。