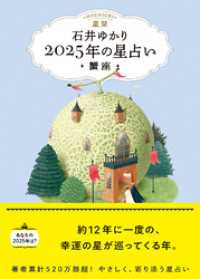目次
詩集『わが出雲・わが鎮魂』から
詩集『倖せそれとも不倖せ 続』から
詩集『「月」そのほかの詩』から
詩集『かつて座亜謙什と名乗つた人への九連の散文詩』から
詩集『牛の首のある三十の情景』全篇
詩集『駱駝譜』から
詩集『春の散歩』から
詩集『死者たちの群がる風景』から
詩論・エッセイ
詩人論・作品論
著者等紹介
入沢康夫[イリサワヤスオ]
1931年島根県松江市生れ。東京大学文学部仏文科卒。1955年大学在学中に詩集『倖せそれとも不倖せ』を出版。以後、詩集に『季節についての試論』(1965、H氏賞)、『わが出雲・わが鎮魂』(1968、読売文学賞)、『死者たちの群がる風景』(1982、高見順賞)、『漂ふ舟』(1994、現代詩花椿賞)、『遐い宴楽』(2002、萩原朔太郎賞)など多数。宮沢賢治、ネルヴァルなどの研究でも名高い
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
misui
8
我々の身体を多くの分子が構成しているように、言語は起源を忘れ去られた複数の引用からなるシステムである。それを検証するかのごとく自身の詩に注釈を施し、誰が、どの作品が詩の裏側でざわめいているかを明かしてみせる(あるいは意識的に取り込む)。作品の根源への接近そのものを作品化する姿勢は個人史を描きもし、出身地である神話の地・出雲への地獄下りの様相を呈する。宮沢賢治やラフカディオ・ハーンらを道連れに、死者のざわめきの彼方、名付けえないその場所へ。なかなかに取っ付きにくいがその足取りには見るべきところが多い。2014/04/30
misui
6
併録の「作品の廃墟へ―幻想的な作品についての妄想的な断想」を何度か読む。真に幻想的な作品が持つ幻惑(詩)、それは瞬間的なものであって、叙述の時間性と対立する。だが幻想を叙述する以上、語りとは不可分(なので往々にして散文形式をとる)で、特殊な形式が必要なのではないか。幻惑が語りを喰い破る…作品の常識的完結性を喰い破る形式。たとえば語りの断片化、中断など。2014/05/07
水紗枝荒葉
3
『わが出雲・わが鎮魂』(1968年)と『牛の首のある三十の情景』(1979年)は日本現代詩のハイライトと言ってもよい。モダニズム的な方向性はここで限界まで突き詰められた。そして時代の磁場を失った(現代詩の活動が活発だったのは60年代までで『牛の首』の時点でだいぶ盛り下がっていた)入沢は、二度とこのような「重い」作品を書けなかったのである。2024/03/15
Reidemeister_Roseman
0
単純に組版の観点から、千木の形に文字が配されたり、上下反転したテクストが挿入される『わが出雲・わが鎮魂』が面白かった。他には『かつて座亜謙什と名乗つた人への九連の散文詩』、『牛の首のある三十の情景』に興味を引かれた。2023/10/10
odmy
0
藤井貞和や吉増剛造みたいに古典の知識を散りばめた詩が好きなのだけど、この詩集にはあまり惹かれなかった。ちょっとまじめ過ぎて、平凡過ぎるというか…。もう少しぶっ壊れた感じだと好きになれたと思う。後ろの方にある詩論はそこそこ面白かった。そこで言われている、作品が未完だから幻想的作品のうさんくささから脱却できるという指摘は鋭い。でも、この人自身の作品は完成され過ぎている。そこが物足りなさの原因なんじゃないだろうか。2023/05/13