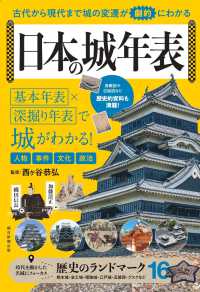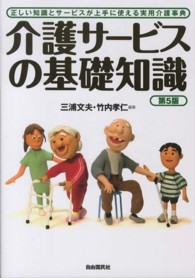内容説明
「それなら、ぜひ、母の世話を…」「仕事は100の内、97まで退屈で大変かな。でも、3つくらいは面白いことがあるかもしれない」そんなふうに友人から頼みこまれて始まった介護ヘルパーとしての生活。頼んだ友人は、老いた母に自らの最後の命を注ぎ込むようにして先立った。“かたわれ”としての母娘―。「だいじょうぶよ、スミさん」は、残された命に寄りそう魔法のことば。老人介護の場で立ち会った命の行き交いを淡々とつづる表題作のほか、遠く近くに生きる人びとへの共感にあふれた18篇を収録。日々の暮らしをてがかりとして、筆者の思いは、子どもたちへ、女たちへ、障害をもつ人びとへ、そして、時代の苦難を生きる人びとへとつらなってゆく。
目次
だいじょうぶよ、スミさん
下着のたのしみ
赤いナップッザック
魔法の財布
闇の菜の花―『女と刀』の初女
背すじのばして―「東京こむうぬ」武田美由紀
「水俣」の母―坂本フジエさん
草の実のようにつよく―「草の実会」松山貞子
老年はまさに熟年―「声なき声の会」望月寿美子
勉強は一生もん―「大阪民話の会」徳井セツ子
やまのかみデモの記
夢の子どもの館と現実
水俣病センターのためのバザー始末記
子どもがとりもつ地縁
生命の露が尽きるとも
信念を貫くこと
ゆったりと「いい加減」に
浦河べてるの家
著者等紹介
熊谷順子[クマガイジュンコ]
1931年、大阪生まれ。戦争中、和歌山高等女学校へ疎開。校庭でサツマ芋をつくり、ミーリング工場で働く。日本女子大学史学科に在学中は、勉強より名画座通いに熱中。8畳に3人の寮で暮らす。1958年、熊谷光之(粕三平)と結婚。2児を育てながら、水道屋トレース、東京電力パート、草の実会事務を経て、岸野スミさんのお世話に13年通う。現在、埼玉県新座市精神障害者家族会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。