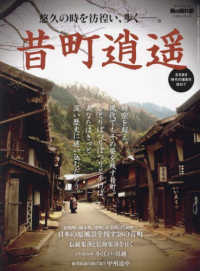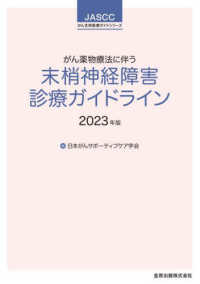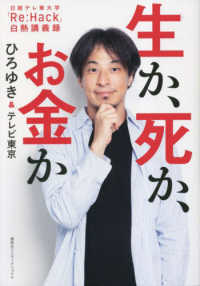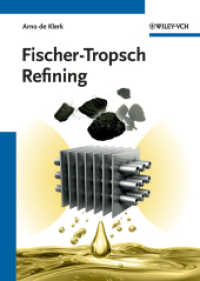内容説明
人間は人間をどのように理解していたか。人間の本質とその行動を理解したいという願望は、人類の永遠のテーマである。このテーマをめぐっての思索の歴史を紀元前までさかのぼり、下っては近年の心理人類学、エソロジーまでをも視野におさめた人類学史。
目次
第1章 初期の段階
第2章 中世の人間観
第3章 開けゆく地平線
第4章 学問の興隆
第5章 人が学ぶべきは人
第6章 理性の運命
第7章 タイラー以前における展開
第8章 タイラー、モーガン、フレーザー
第9章 伝播と移住
第10章 機能主義
第11章 米国の人類学
第12章 人類学と人種の概念
第13章 心理人類学
第14章 新しい人類学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
3
人類学史。といっても、細分化前の広い意味での人間学史で、古代ギリシアから中世まで遡る。自然と並んで、やはり人間にとっては人間自身が興味深い対象であった。当然といえば当然だが、人類が「類」であるためには、まずは他のものと区別されることが前提となる。物質的環境や他の生物とは異なる(と同時に人間同士は斉一性をもつ)ことが発見されないとならない。自然の一部でありながら文化によって自然から離れていくこともできる存在というのが、この人間性の根拠であるが、自然と文化の関係は揺れ動く。そして人間の自己理解も変転を重ねる。2019/05/17
ppp
0
とりあえず6章までの部分は、概論としては多少有用だった。後半の、19世紀以降の諸学問が関わる箇所は、後でもう少しまじめに読みたい。2014/09/30