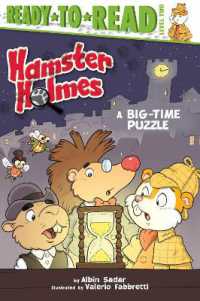目次
第1章 近代「芸術」の終焉
第2章 「美しい芸術」と精神の美学
第3章 なにが「アート」か?
第4章 「作品である」ことの実質
第5章 作品の論理的身分
第6章 フィクションの快楽
第7章 歴史と物語
第8章 趣味と批評
第9章 キッチュと悪趣味
第10章 写真メディア―視覚の変容
第11章 ポップの美学
第12章 美的多元主義の時代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Meme
12
めちゃくちゃ良い本なんだと思う。何度も読み返したい類のもの。 実生活のなかで美的判断がなされるとき、〈美しい〉、〈きれい〉等のごとき形容詞がほとんどなんの役割もはたしていないのは、驚くべきことである 空虚なだけの感嘆詞を多用する人生からおさらばしたい。2023/10/24
オザマチ
11
アートに関する色々な価値観の変遷を追った上で、現代アートについて考える。話の筋とは関係ないが、自分が美術館で実際に目にした作品も取り上げられていて、ちょっと嬉しい。2021/02/10
koke
9
再読。タイトルから想像されるような現代アートについての芸術哲学には留まらない。悪趣味なものや広告なども含めた、現代人の美的経験についての美学でもある。ポストモダン状況の理解がメインテーマであり少々古いが、ちくまあたりで増補改訂して文庫化したら有意義だと思う。2025/10/11
TOMYTOMY
3
芸術学部の人たちが読んでて気になりながらやっと読めた。 非常に素晴らしい内容かつアートの根本的な理解に繋がるとともに、それ以降の00年代以降を踏まえてアップデートするようなものが欲しい。 誰か知ってたら教えてくださいw2022/02/26
日輪
3
曖昧な単語や感覚的な主張が多く、真面目に受け取れそうな文章は半分位だったけど、扱う内容が多いので勉強になった。社会学や仏現代思想を知らないと読み辛いかも。「芸術」が近代の「啓蒙」的思想から生まれ、科学の発達と大衆社会を経て、現代の「アート」が自己「主張」する様子、客観的「事実」を描く「歴史」と、「虚構」性を含む「文学」が分かれていく様子、趣味や価値は社会と個人の両面から、あるジャンルに固有の基準に従って決まること、そしてなおもアートが芸術のような精神性や神秘性を重んじる傾向があること、などが分かった。2015/12/16