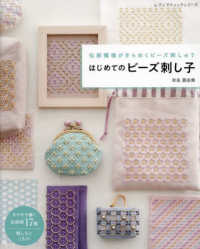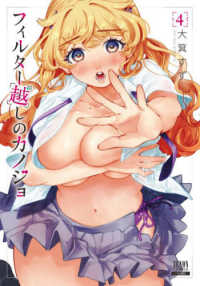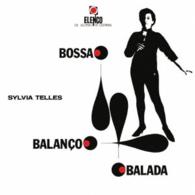出版社内容情報
様相論理学を基礎に新たな形而上学の可能性を追求してアメリカ哲学界を震撼させた現代哲学の「古典」。
同一性の必然性,固有名の固定性,指示の因果説の独創的な三テーゼを軸に,論議は自然種および心身問題に及ぶ。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
33
講義録のわりには導入が回りくどいので、55ページから読み、それ以前は飛ばして読んだ方が良いと思います。固定指示子とは、それ例外ではあり得ない性質のことです。太陽系の惑星は9つではなく7つであることは想像できる(実際のところ現在惑星は8)。この様な可能世界で起こる性質と、可能世界にまたがる同一性の性質は異なる。名前は固定指示子である、というのがクリプキの主張です。2021/09/04
みのくま
7
本書の命題は「名前」をどのように定義するかという事である。フレーゲやラッセルは、個体の「諸性質の束」として捉える事で説明しようとした。だがクリプキは「名前」を固定指示子であるとする。例えば複数の可能世界があるとして、各世界に存在する同一の人物を同じ名前で名指す時、諸性質の束で定義付けようとすると不可能になる。そうではなく、性質とは無関係にそこには同一人物であるアプリオリかつ必然性があるのだいう。いわばクリプキは「本質主義的形而上学」を復権しようとしたのだ。とはいえ、分析哲学は正直いまいち理解できていない。2022/09/15
大道寺
4
プリンストン大学で1970年1月に行われた3回の講義を基にしている。固有名は確定記述の束であるとする理論に対する批判の書である。本書において、クリプキは従来の理論が正しくないことを指摘するが、それに代わる理論を提出するわけではない。ただ、従来の理論を乗り越えた先へ行くための見取図のみを提示する。(1/5)2012/10/21
有沢翔治@文芸同人誌配布中
3
分析哲学の本で、フレーゲ-ラッセルとジョン・スチュアート・ミルの固有名についての考えが整理されている。また論旨も一貫性があり極めて解りやすい。ただ分析哲学はそこまで興味を抱けない。確かに考え方としては評価できるし、数学的な要素があって面白いんだけど。https://shoji-arisawa.blog.jp/archives/51443275.html2014/11/22
hryk
1
分析哲学の古典。最後の方で指示の問題の応用として展開される心身問題についての議論は改めて読むとけっこう面白い。2023/10/30