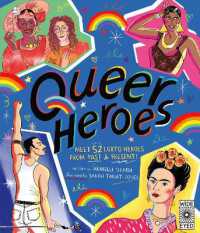内容説明
本書では、ステレオタイプの形成や維持のメカニズム、そして具体的な研究例をもとに解消の方法を探っていく。
目次
1 ステレオタイプ・偏見とは
2 ステレオタイプ・偏見が生じる背景
3 ステレオタイプ維持のメカニズム
4 否定的ステレオタイプ・偏見をもたれる側の心理
5 ステレオタイプ・偏見はどのように変わるのか
著者等紹介
上瀬由美子[カミセユミコ]
1988年日本女子大学文学部卒業。1993年日本女子大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。現在、江戸川大学社会学部助教授博士(文学)。専攻は社会心理学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小木ハム
10
事実と異なることでも一度ステレオタイプが定着してしまうと拭い去ることは難しい。身近なものだと、血液型性格診断は科学的な根拠ゼロで否定されているにもかかわらず市民権を得ている(世界広しといえど日本だけ)。この分野の包括的な視点からの解説が主で、研究事例が豊富で資料としても良い本だと思う。ステレオタイプや偏見を完全に無くすことは不可能だが、ネガティブ要素の促進を抑えることはできる。やっぱり、サマーキャンプ実験に代表される『協同、共通の敵、相互依存関係』がかなり効果的で、あとは精神的なゆとりを持つことも大事。2022/07/07
nranjen
4
文学の領域で以前読んだステレオタイプの説明と重複している。何か原典的なものはあるのか?リップマンが重要であることが確認された他、フロムやアドルノなどやはり読んでおかなければならないことを痛感。2018/04/12
ゆうか
2
ステレオタイプについて多角的な角度で述べた1冊。社会的にスティグマを被っていると自覚している人に対して単に肯定的に接しても真に伝わらなかったりするという点が面白く難しいなぁと思った。また、私はどんなに科学的根拠がないと言われても血液型性格診断を信じてしまっているのだが、思い返してみると確かに血液型が当たった経験がありサブカテゴリー化していると感じられた。2021/11/21
たけみ
2
レポートの参考資料として読了。身近なステレオタイプや偏見の事例が、様々な実験結果とともに紹介されていてとてもためになった。実際に偏見を解消していくのは簡単ではないのかもしれないが、希望をもって少しずつ取り組んでいくことが大切だと感じた。2015/07/30
Takanobu Y
2
ステレオタイプ化を避けようとすることが、その後のステレオタイプ化を促進することになる。 そういうことは、経験的にある。 参考になった。2012/06/14