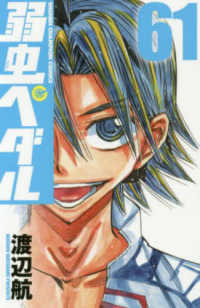出版社内容情報
小川裕夫[オガワヒロオ]
著・文・その他
内容説明
新宿駅と品川駅、首都圏最強ターミナルはどっち?渋谷駅と池袋駅、これから伸びる副都心はどっち?築地駅と豊洲駅、集客力が期待できるのはどっち?蒲田駅と浅草駅、オトナが楽しめる歓楽街はどっち?梅田駅と難波駅、ターミナルとして将来性があるのはどっち?…など、利用客の視点からはわからない主要駅の「本当の実力」と将来性を、鉄道ライターとして知られる著者が徹底分析。鉄道と駅の歴史がわかれば、街の見方が変わる。
目次
はじめに 「駅の力」を見れば、街の魅力度がわかる
第1章 なぜ、「ライバル駅格差」が生まれたのか?(なぜ、「田園調布」は高級なイメージなのか;小田急江ノ島線に三つの「林間駅」が並ぶ理由 ほか)
第2章 首都圏22駅ライバル対決(「相互乗り入れ」の発達で激変する駅格差;秋葉原駅に見る「拠点力」の移り変わり ほか)
第3章 これから“伸びる駅”を見極めるために(時代ごとに変わる「山の手」「下町」の定義;「金曜日の妻たちへ」が描いた郊外マイホームの時代 ほか)
第4章 全国3大都市14駅ライバル対決(大阪ライバル駅対決;名古屋ライバル駅対決 ほか)
著者等紹介
小川裕夫[オガワヒロオ]
1977年、静岡県静岡市生まれ。行政誌編集者を経てフリーランスライター。取材テーマは地方自治、都市計画、内務省、総務省、鉄道(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。