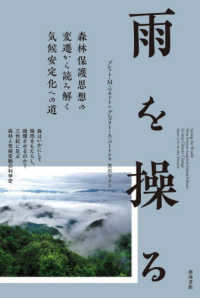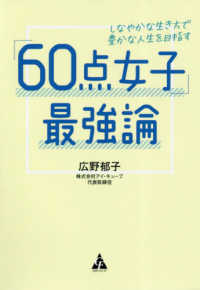出版社内容情報
日本酒はふしぎ。
日本酒にいろんな味わいがあるのは、なぜだろう?
呑む文筆家が名酒のふるさとをめぐり、その味の秘密に迫る。
これまでになかった、日本酒紀行エッセイ。
「本書は、私がおいしいと感じた日本酒の産地を旅する放浪記いや「呑浪記」だ。酒縁や時間の流れに身を委ねたマイペースな酒の旅である。日本酒の酒蔵は全国に散らばっているが、一県一銘柄などというような全国制覇は目指さない。東西南北エリアのバランスもあまり考えていない。あくまでも時々の酒縁や、「おいしい」と自分の体が反応するかどうかの本能的な感覚に従って行き先を決めた。」(「はじめに」より)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【本書で訪ねたお酒】
・AKABU(岩手)……朴訥な岩手っ子が堅実につくりあげた人気銘柄
・七福神(岩手)……若きリーダーが挑戦する古くてあたらしい酒
・七重郎(福島)……人知れず歴史を重ねてきた猪苗代に唯一残る地酒
・廣戸川(福島)……コツコツ酒を磨いた先に着実なヒットが待っている
・冩樂(福島)……「俺の酒」から兄弟で手がける共生の酒へ
・群馬泉(群馬)……寝かせてつくる癒しの酒
・喜正(東京)……東京の山奥で醸すたっぷりの旨み
・開運(静岡)……飾らない、一徹した「いい酒」づくり
・白隠正宗(静岡)……ぺろっと一升飲める地酒を追求する酒蔵
・剣菱(兵庫)……500年変わらない酒質を口伝で紡ぐ
・神雷(広島)……気温・水・微生物、自然の摂理に逆らわない酒造り
・賀茂金秀(広島)……きれいな喉越しをつくる「健全な発酵」
・雨後の月(広島)……蔵元と杜氏のシビアな緊張で出せる味
・天狗舞(石川)……震災をのりこえる蔵と蔵のつながり
・獅子の里(石川)……どん底を乗り越えたからこそ、生まれた奇跡の酒質
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
内容説明
日本酒にいろんな味わいがあるのは、なぜだろう?呑む文筆家が名酒のふるさとをめぐり、その味の秘密に迫る。
目次
朴訥な岩手っ子が堅実につくりあげた人気銘柄―AKABU
若きリーダーが挑戦する古くてあたらしい酒―七福神
人知れず歴史を重ねてきた猪苗代に唯一残る地酒―七重郎
コツコツ酒を磨いた先に着実なヒットが待っている―廣戸川
「俺の酒」から兄弟で手がける共生の酒へ―冩樂
寝かせてつくる癒しの酒―群馬泉
東京の山奥で醸すたっぷりの旨み―喜正
飾らない、一徹した「いい酒」づくり―開運
ぺろっと一升飲める地酒を追求する酒蔵―白隠正宗
500年変わらない酒質を口伝で紡ぐ―剣菱
気温・水・微生物、自然の摂理に逆らわない酒づくり―神雷
きれいな喉越しをつくる「健全な発酵」―賀茂金秀
蔵元と杜氏のシビアな緊張で出せる味―雨後の月
震災をのりこえる蔵と蔵のつながり―天狗舞
どん底を乗り越えたからこそ、生まれた奇跡の酒質―獅子の里
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
toshi
げんさん
みんな本や雑誌が大好き!?
nakopapa
Humbaba