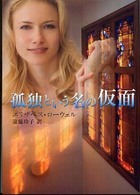出版社内容情報
斎藤恭一[サイトウキョウイチ]
著・文・その他
内容説明
教授の仕事は、“研究”と“講義”だけではない。高校生や予備校生、さらには市民への“広報活動”の仕事。法人組織の一員として担当する“管理運営”の仕事。そして、研究に付随する、科研費の確保や産学連携、学生への生活指導や文章添削…。教授はただの研究者ではなく、“勤め人”であり、“教育者”である。
目次
序章 「大学崩壊」と嘆いても始まらない
第1章 未来ある高校生に必死でPR
第2章 市民にも「理科」に馴染んでもらおう
第3章 「学生指導」はテンヤワンヤ
第4章 大学という「組織」の経営は悲喜こもごも
終章 「研究」は一人では成し遂げられない
著者等紹介
斎藤恭一[サイトウキョウイチ]
1953年、埼玉県生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業、東京大学大学院工学系研究科化学工学専攻修了。東京大学工学部助手、助教授を経て、2019年まで千葉大学工学部教授を務める。現在、早稲田大学理工学術院客員教授。専門は、放射線グラフト重合法による高分子吸着材の開発。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
73
千葉大教授の著者は、高校や予備校に模擬講義に行ったり、市民講座に出かけたりと、大学のプレゼンスを高めるために血の滲む努力をされている。学内では、学生という「未熟者」と格闘し、教授会などの組織運営に翻弄され、そして、研究資金の獲得に汲々となる。そんな大学教授の悲しい生態を、面白おかしく綴ったエッセイである。「理系こそ国語と英語」という先生の信念には賛成。でも、自らをサービス業だとし、ここまでして手取り足取り学生に阿っている大学の姿は、大学の権威と戦った世代から見ると、滑稽であり、また、悲しくもある。2020/08/15
香菜子(かなこ・Kanako)
27
大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 。斎藤恭一先生の著書。斎藤恭一先生が研究者としても教育者としても広報担当者としても誠心誠意全力で奮闘されていることがわかる良書。大学教授というと高学歴で上から目線で偉そうな態度で研究や研究生活に没頭している世間知らず人間というイメージを持っている人もいるかもしれないけれど、研究や研究生活だけに集中できるなんて大きな勘違い。斎藤恭一先生のような大学教授が増えればそういう勘違いをしている人も減っていくでしょうね。2020/09/26
assam2005
21
大学の教授のお仕事ってどんなのなの?大学で研究しつつ大学生に講義をするだけではなく、その他いろんな活動がある。未来の教え子となるかもしれない高校生達に大学をアピール、自分の後輩となる教授の卵に対する人事や指導、ド素人の市民への噛み砕いた講義等など。いろんな学部の中でも人気がイマイチな工学部の教授が学生の人気を獲得すべく、日々地道な活動を続ける奮闘記。大学の人気ではなく、本当にその分野でやりたいと思い入学してくれる学生に来てもらうにはホント大変なのね。知らない仕事の地味な部分が見えるのは面白かった。2025/03/05
kei
21
理系の大学教授と言えば、研究に没頭してて社交的ではなくて…というイメージを持ちがちですがこちらの著者、斎藤氏は不人気学科における学生確保のために日々四苦八苦した25年間他をまとめたエッセイ。高校や予備校を約120校回って、平均80名/回の生徒、保護者に出会ってるとして、1万人の中から著者の研究室にやってきた学生は3人…。現実はとてつもなく厳しい。最終章は研究の予算獲得について書かれていますがたくさんの予算を獲得することのメリット デメリットも書かれていて興味深かったです。2020/10/08
uniemo
15
千葉大学は国立大学の中で志願者数1位とニュースで聞いた気がするのですがその工学部の中でも教授が学生集めに奮闘する不人気学科があることを知りました。著者は自分の研究にも産学連携や学生への指導にも熱心で良い先生です。浪人することも厭わず勉強だけではない高校生活をおくることが創造的な研究を産みだす強みとなり、就職にも繋がっていくというのは年を経た今だとよく理解できました。2021/02/20
-

- 和書
- 思考力アップ算数小3