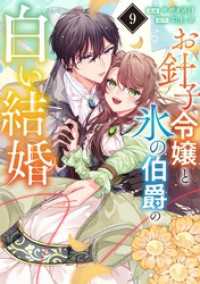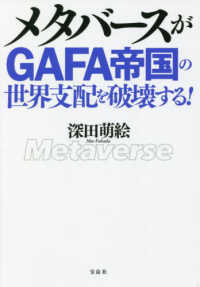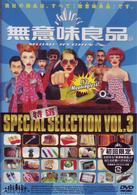- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
海老原嗣生[エビハラツグオ]
著・文・その他
内容説明
これから15年で仕事の49%が消滅する…?将来的に9割の仕事は機械に置き換えられる…?世間をにぎわすAI論議は、どこまで妥当なのか。AIによる雇用への影響は、どのように広がるのか。実務者への取材と、雇用構造の検証でひもとく、足元の未来予想図。
目次
1 しっかり振り返ろう、AIの現実(ただいま人工知能は第3回目のブーム;ディープラーニングもAI進化の通過点でしかない ほか)
2 AIで人手は要らなくなるのか、実務面から検証する(AIで仕事はどれだけ減るか1 事務職の未来;AIで仕事はどれだけ減るか2 流通サービス業の未来 ほか)
3 この先15年の結論。AIは救世主か、亡国者か(少子化と人口減のヤジロベエ状態;いよいよ労働力確保策も限界に ほか)
4 15年後より先の世界。“すき間労働社会”を経て、“ディストピア”か?(雇用消滅への2ステップと、BI型生活へのウォーミングアップ;日本は「塞翁が馬」的な移行期となる ほか)
著者等紹介
海老原嗣生[エビハラツグオ]
雇用ジャーナリスト、経済産業研究所コア研究員、人材・経営誌『HRmics』編集長、ニッチモ代表取締役、リクルートキャリア社フェロー(特別研究員)。1964年、東京生まれ。大手メーカーを経て、リクルート人材センター(リクルートエージェント→リクルートキャリアに社名変更)入社。新規事業の企画・推進、人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて人材マネジメント雑誌『Works』編集長に。2008年、人事コンサルティング会社「ニッチモ」を立ち上げる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なかしー
なるみ(旧Narumi)
hk
ま
Yuichiro Komiya