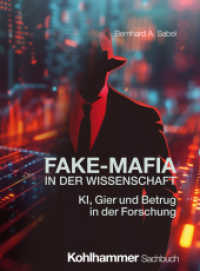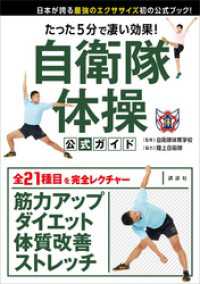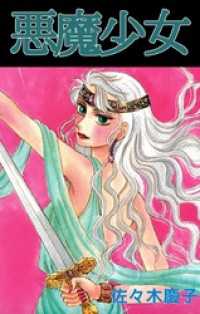出版社内容情報
★ 「うつわ」の魅力を引き立たせる多様な背景を
徹底解説。
★ 全国の窯場・産地の見どころや作品の特徴、
土や釉薬の性質など
◇◆◇ 監修者からのコメント ◇◆◇
日本各地の「やきもの」には、それぞれ個性がある。
その個性を形づくるのは、
それが生まれる土地の風土であり、
やきものが持っている歴史である。
平安時代末から鎌倉、室町という中世は、
やきもの生産が盛んな時代だった。
壺、甕、鉢を焼いた中世の窯跡は、
日本各地に80カ所以上も確認されている。
桃山、江戸時代初期には、茶の湯の流行を背景に、
釉を掛け、文様を描いた陶器が続々誕生。
それらは茶道具だけでなく食器へと展開し、
やきものの活躍は生活道具から、
もてなしの場へと広がった。
さらに江戸後期には、陶磁器の普及によって
各地でやきもの生産が盛り上がる。
藩の主導で製作する高級品、
暮らしに寄り添う日用の器など多種多様。
そうした、それぞれ異なる歴史が各地の
やきものの背景にある。
中世の焼締陶・備前焼、桃山の茶陶・美濃焼、
江戸の民窯・益子焼。
新しいものが生まれれば古いものが消えていく、
とは限らないところが面白い。
それが日本のやきものの多様性へとつながっている。
多くの窯が長い歴史のなかで消えていった。
生産力や流通で競争があったり、
生活様式の変化でやきものが使われなくなったり。
ところが、それらを乗り越え存続する窯、
さらには復活する窯がある。
技術は途絶えるし、原料の土もその土地のものを
使い続けるとは限らない。
それでもなお、やきものづくりの記憶のある場所で、
やきものがつくられ続ける。
思えば不思議なことである。
その土地へ行って、景色を眺め、風を感じ、食べて、
話して、暮らす人々の思いに触れて。
そうして、初めてわかるかもしれない。
謎は解けるのか深まるのか。
でもそこには、きっと新しい発見がある。
さあ出かけよう、やきものの旅!
陶磁研究家
森 由美
◇◆◇ 主な目次 ◇◆◇
☆ 巻頭特集
やきものの町を訪ねる
* 丹波焼 〈兵庫県丹波篠山市〉
* つくり手に会いに丹波焼の里へ
* 見て食べて触れて、やきものの町を歩く
・・・など
☆ 第1章
やきものの基礎知識
☆ 第2章
全国の窯場でやきものを楽しむ
☆ 第3章
ほかにもあるやきものの里
内容説明
全国の窯場・産地の見どころや作品の特徴、土や釉薬の性質など、「うつわ」の魅力を引き立たせる多様な背景を徹底解説。
目次
巻頭特集 やきものの町を訪ねる(丹波焼(兵庫県丹波篠山市)
つくり手に会いに丹波焼の里へ ほか)
第1章 やきものの基礎知識(やきものができるまで;磁器・陶器・焼締の違い ほか)
第2章 全国の窯場でやきものを楽しむ(会津本郷焼(福島県大沼郡会津美里町)
笠間焼(茨城県笠間市) ほか)
第3章 ほかにもあるやきものの里(こぶ志焼(北海道岩見沢市)
津軽焼(青森県弘前市) ほか)
著者等紹介
森由美[モリユミ]
陶磁研究家。東京藝術大学大学院美術研究科修了。戸栗美術館学芸員として勤めた後、日本陶磁協会で専門月刊誌『陶説』を編集。現在、陶磁器や伝統文化に関する執筆、講演、調査を行う。戸栗美術館学芸顧問、女子美術大学非常勤講師、NHK文化センター講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
FOTD
北緯45°
きのたん
kaz