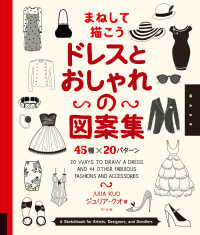出版社内容情報
★ 動画で「イロハ」からわかりやすい
* お茶会にお呼ばれしたら
* 茶室での振る舞いや所作
* お茶席での会話
★ もっと広がる興味と知識
* 茶事と道具のいろいろ
* 和菓子との深い関係
* 自宅で楽しむお点前
★ 間違えないことよりも、心をこめること。
★ 形式よりも、自分らしくもてなし、愉しむこと。
◆◇◆ 茶の湯について ◆◇◆
今からおよそ1300年前に中国から伝わった
茶ですが、それから約400年後に栄西禅師により
佐賀県の背振山に茶の樹が植えられ、
抹茶法が伝えられたころから、
一般に飲まれるようになったといわれています。
抹茶法とは、茶碗に直接茶の粉を入れ、
これに湯を注いでかき混ぜて飲む方法で、
今の薄茶に近い飲み方と思われます。
その後、幾多の茶人の手を経て、
千利休によってわび茶が大成されました。
茶の湯は「一服の茶を飲む」ことを目的としながら
そこには日本の美、日本人の心に出会うことができます。
それはまるで美の玉手箱です。
まず、目にするのは「自然の美」でしょう。
。茶室という小さな空間の中で、
一輪の花の命の輝きにふれながら、お茶をいただきます。
そして「道具の美」です。
茶碗、茶杓、釜…。
茶の湯に使われる道具は時代を映し、
様々な茶人の手を経て伝えられてきました。
陶工からのメッセージが伝えられ、
心がひとつになる充実感がもたらされます。
「室礼の美」にも感動します。
光と陰の美しさも見逃せません。
光を遮った空間でいただくお茶は、
心に落ち着きをもたらしてくれます。
まだあります。茶を点てる「所作の美」です。
ひとつひとつの動作には美しい型があり、
その動作がおいしい茶を点てるにつながるのです。
最後に美の玉手箱で見つけたのは
「亭主と客でつくる美」です。
一服のお茶を通して、美を分かち合い、
美をつくっていく。
それが「茶の湯」です。
◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆
☆ 1章 茶会へ行こう
☆ 2章 道具を楽しもう
☆ 3章 茶会を開こう
※本書は2018年発行の
『DVDで手ほどき 茶道のきほん 「美しい作法」と「茶の湯」の楽しみ方 新版』
を元に、動画の視聴形態を変換し、
必要な情報の確認と書名・装丁の変更を行い、
新たに発行したものです。
内容説明
動画でイロハからわかりやすい―お茶会にお呼ばれしたら、茶室での振る舞いや所作、お茶席での会話。もっと広がる興味と知識―茶事と道具のいろいろ、和菓子との深い関係、自宅で楽しむお点前。間違えないことよりも、心をこめること。形式よりも、自分らしくもてなし、愉しむこと。
目次
1章 茶会へ行こう(茶会って?;茶会体験初級 薄茶をいただく;茶会体験上級 正式な茶会(茶事)へ)
2章 道具を楽しもう(道具って?)
3章 茶会を開こう(茶の湯を楽しむ「自分流」で;茶会を開くPart1 薄茶とお菓子でおもてなし;自宅で茶会を楽しむ;茶会を開くPart2 落合流懐石料理と濃茶でおもてなし)
著者等紹介
太田達[オオタトオル]
茶人・有職菓子御調進所老松主人。公益財団法人有斐斎弘道館理事。工学博士。立命館大学食マネジメント学部教授。江戸時代の学問所である有斐斎弘道館において、茶文化をはじめ各種講座を開く。国内外で話題になる茶会を数多く開く。専門は茶道文化論、食文化、伝統産業論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめぴょん
福ノ杜きつね