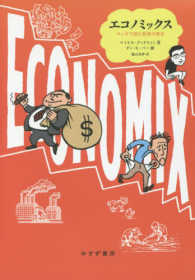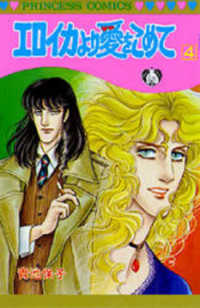内容説明
だれもが安心していられる学校をつくるために。専門性の異なる多職種が、協働して取り組むために。子どもや保護者にもリアルに届く共通言語を求めて。新しい支援の理念にふさわしいあり方を模索する。
目次
第1章 子どもたちはなにを求めているのか(謙虚な問いかけが子ども理解を深める;多職種協働における資質・能力―学校福祉の視点)
第2章 学校と福祉・心理をつなぐ「ことば」(しあわせな不登校;在宅児童生徒;複雑な家庭;声かけ事案と気づきを促す言葉;情報共有;問題を「経験している」;謝罪・許し・赦し;事実としての福祉;地域の福祉的施設としての学校;「チーム学校」と教育職;かさなりへの気づき)
第3章 学校福祉の視点―どんなときに協働が始まるのか(保護者の葛藤が協働を橋渡しする;見立て(アセスメント)をチームづくりにつなぐ
俯瞰し、一歩下がってものを見る
仮説・検証・調査)
著者等紹介
鈴木庸裕[スズキノブヒロ]
日本福祉大学教育・心理学部教授。福島大学名誉教授。学校福祉士、社会福祉士、学校心理士。日本学校ソーシャルワーク学会理事、福島県教育委員会他スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザー、日本学校心理士会福島県支部長、他。全国10自治体のいじめ問題調査委員会委員長など。学校が子どもたちの福祉(しあわせ)にいかに責任を負うのか。学校の教育・福祉的機能を教育職、心理職、福祉職などが一緒に高めていく「学校福祉士」を提唱している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。