内容説明
子どものための居場所が、おとなの過剰な管理や配慮、そして社会の同調圧力によって奪われてはいないでしょうか。子どもがのびのびと生きられ、同時に地域社会を豊かにしていくような「まなざし」のあり方を考えます。
目次
第1部 居場所を喪失した現代社会
第2部 居場所をはぐくむ子どもとおとなの距離感
第3部 子どもにとっての学校
第4部 家庭と学校以外にも居場所はあるよ
第5部 子どもの時間、子どもの自然
第6部 子どもが育つ社会の構造―子どもがもっている「育つ力」を信じる
著者等紹介
阿比留久美[アビルクミ]
早稲田大学文化構想学部准教授。博士(文学)。社会教育と社会福祉を結びつけて研究しつつ、若者協同実践全国フォーラム(JYCフォーラム)で活動中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
56
子どものための居場所が、大人の過剰な管理や配慮、社会の同調圧力により奪われる現状。子どもがのびのびと生きられ、地域社会を豊かにしていく「まなざし」の在り方を考えた書。<「コミュ力」の多寡が様々な場で問われ続け、他者とうまくやっていくことができないことを「コミュ障」などと言って自分や周りの人たちを嘲笑することが日常化している子ども・若者たち。彼らが、他者ではなく、自分の内的世界と対話できるようなゆとりと機会をもてるようにしていくことが、自分を耕す「居場所」づくりを支えるのではないでしょうか>。大賛成です。⇒2022/06/15
katoyann
18
社会教育を専門とする学者による居場所に関する論稿。効率と効用ばかりを求める社会の中で、子どもが遊びを通して成長していく過程が奪われているという状況を分析している。フリースクールから子ども食堂まで考察対象が幅広いのも本書の特徴である。子育て経験などの自らの体験を織り交ぜながら、社会学や心理学の専門用語を挙げて事例の分析を展開している。子どもが多様な価値観を身につけて、自己肯定感を高めるためには、家族や教員だけではなく、色々な大人に出会う機会が必要だとする話が面白かった。2025/04/14
いとう
9
居場所を「居たい」「居られる」「居なければならない」で考えたときに、それぞれのはざまで子どもにとっての学校の体験がどのように異なるかを説明(82)。 学校の持つ同調圧力にしたがうことによって、いなくてはいけない場所である学校に自分がいられる状態を維持しようとする神経戦…(92) 平田オリザ(わかりあえないことから 講談社現代新書)のp183の意見に居場所ある社会づくり、文化づくりの鍵があるように(筆者は)思う(95) 2023/11/24
みさき
4
居場所という概念を定義づけることは難しいけれど、とても参考になった。 地縁、血縁が薄くなり、人間関係の形成・維持を自らが選択して生きていく選択的関係の中で生きていく現代の人々は、家族以外のつながりが薄く、家族へ頼ることが出来ない時に他に誰も頼ることが出来ない環境に置かれている。このような時代だからこそ、ある場所に行けばいつも会う人、話す人がいる、顔を合わすだけの人もいるという「居られる場所」としての第三の居場所が必要なのではないか。 2025/04/04
saiikitogohu
3
引用が良いから、バックガイドになるなと。【劇作家の平田オリザさんは、現代日本社会が、社会の多様化、グローバル化に対応するための「異文化理解能力」と日本型の「同調圧力」のダブルバインドにあっている、と述べています】94【義務や責任を説かなくても、自分たちのこと、自分たちの居場所のことだという自覚さえあれば、子どもは自らその責任を引き受けていきます】111【先回りしてトラブルを取り除くのではなく、むしろトラバルに直面するのを妨げず、一緒になって対処法を考えていく…「苦労する権利」を奪わないという実践】1182023/01/09
-
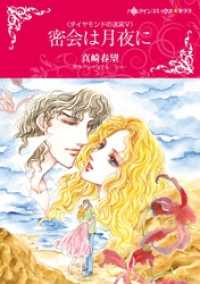
- 電子書籍
- 密会は月夜に〈ダイヤモンドの迷宮Ⅴ〉【…








