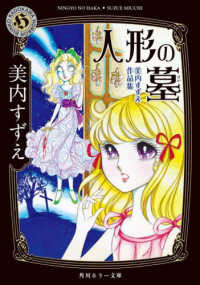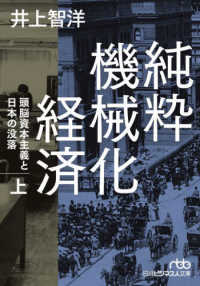内容説明
日本政府の覚悟に不安を抱いたアメリカ、自衛隊や下請けに任せようとした東京電力、戸惑いながら判断を下すしかない官邸―10年過ぎたから語れる原発事故対応の深層。共同通信社の大型連載(21.3~21.12)の書籍化。
目次
1章 未曽有の危機
2章 科学者長官の見た「3・11」
3章 収束への道程
4章 同盟の試練
5章 戦後最大の国難
6章 最側近の葛藤
7章 国を守る者の覚悟
8章 「緩衝役」の目線
9章 救世主と呼ばれた男
著者等紹介
太田昌克[オオタマサカツ]
早稲田大学政治経済学部卒、政策研究大学院大学で博士号(政策研究)。共同通信社に入社し、広島支局を初任地に外信部、政治部、ワシントン特派員などを歴任。現在は同社編集委員・論説委員、早稲田大学・長崎大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
83
あの未曾有の原発事故から11年。その時、日米政府中枢で何が起こって、いかに対応しようとしていたか?当事者へのインタビューにより振り返る。米国は当事者ではないが、日米同盟、日本居住米国民の安全など諸々の状況から重大な関心を寄せ、米国の国益の為、危機収束への強力な援助を日本政府に提供する。非常に残念ながら日本には原発事故にに対する実践的対策が用意されていなかった。原発建設を推進するためには、原子力に対する非常に敏感な国民感情から具体的事故を想定することはタブーで、それは原発安全神話を作り出すことに繋がった。⇒2022/07/08
yyrn
22
10年以上も前のことをよく詳細に覚えているものだなと驚くが、忘れられないほどの危機的な、一歩間違えば東日本に人が住めなくなったかもしれないほどの「原子力災害」だったのだ、ということを日米9人のキーマンへのインタビューから教えてくれる本。当時の危機対応の混迷ぶりを詳細に残すことで、今後どこかで起こるかもしれない類似の事故に備えるためには非常に貴重な証言だと思うが、しかし、読みながら当時を思い出すので、私にはそれが非常につらかった。この人たちの頭には、すでに津波で亡くなった2万人のことはなく、⇒2022/07/13
紙狸
21
22年3月刊行。共同通信が配信した連載インタビューをまとめた。著者は「核」の専門記者。2011年の福島第一原発事故への対応を検証する。米原子力規制委員会(NRC)関係者など、米国からの人選が手厚いのは著者ならでは。米政府やNRCが事故を深刻に憂慮し、日本側に様々な支援のアプローチをしたことが語られる。混乱していた日本政府の態勢が、米国との情報交換の枠組みを作ることで改善した。情けないとの感想もありえようが、危機管理を巡る日本政府の実力と日米の差を物語っていると受け止めた。2022/06/17
tetsubun1000mg
10
3.11を日本政府の中枢とアメリカの原子力委員会と駐米大使とのインタビューで構成する本。 10年たった今だからこそ語れる真実が見えてくる。 現実をとらえていたのはアメリカが先だった。 日本は放射能の計測器もまともに揃っていなかったし。大洪水への準備もしていなかったのだから。 アメリカは原発事故も経験していたし原子力潜水艦から原子爆弾をも管理していたので常に準備していた差は歴然だった。 菅首相もいろいろと言われたが、菅さんだったから対応できた面もあったようだ。 もちろん当時の政府には準備は全くなかった。2022/05/10
ペンポン
2
読んでガッカリした。原子力に対する危機管理の甘さ。原発安全神話しか考えてない関係者のいい加減さ。対して悔しいけれど、しっかり備えていたアメリカ。また未体験の危機に遭遇した時の対応力の脆弱さ。そしてリーダーたる者はこの様な事態に遭遇した時どう対応すべきか考えた。菅総理は理科系出身を自慢し過ぎて独断と偏見で舵を切った。専門でない分野では専門家に技術的なことは任せて自分は判断だけをすれば良いのだ。現在でも原発の危機管理は忘れてはならない。情報システムに侵入されたら国の安全が脅かされる。大丈夫か?2023/03/13