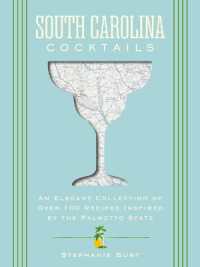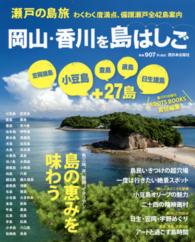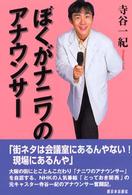内容説明
カーテンを閉め切った部屋で、誰とも口をきかず、昼夜逆転の生活…。ひきこもりというと、ステレオタイプのイメージを抱く人も多い。だが本当にそうなのだろうか。「本人に必ず会いに行く。会えなくても、せめて扉の前までは」国の調査などの数字に表れない実相を探るため、取材班は決めた。
目次
第1章 川崎・練馬事件と8050問題
第2章 横行する自立支援ビジネス
第3章 ひきこもりを地域で支える
第4章 就労に踏み出すとき
第5章 ひきこもる女性たちの苦悩
第6章 全国に広がる家族会
第7章 声を上げ始めた当事者たち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
25
共同通信ひきこもり取材班によるルポ。ひきこもりを自己責任にしてはならないとあらためて思った。社会不適合者としてみることはしてはならない。また、就労支援の難しさや危うさもみてとれた。安心して今を承認しなければならないと思った。2020/01/18
tacacuro
3
「目に見えない生きづらさと、暮らしにくさを可視化し」、ひきこもりの実相を探るルポルタージュ。「私たちはいつ、どのような状態で、ひきこもり状態になるか分からない」「だからこそ誰もが自分事として考えていかなければならない」と。全く同感。2020/01/12
つかほ
2
変わるべきは当人以外だと思った。2020/03/21
アケノ@文化系な日々の記
1
思ったより本が薄く、結果、事例は少なめだと感じた。 ひきこもることで幸せならそれでいい。 踏み出したあとは地域とつながれるか。 この二つのことが印象に残った。2020/01/28
naohumi
1
ひきこもりも一つの生き方。ひきこもりという主体性。という言葉が印象的だった。年密に取材されており、実態がよく伝わってきた。社会誰もが社会資源。変な先入観ではなく、地域がそれぞれの方々を本当に理解していく必要性を思った。2019/12/30