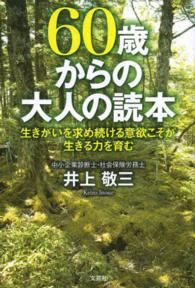内容説明
子ども条例の制定・子どもの権利相談室・子どもの権利擁護委員としての活動をふりかえり、子どもの権利条約や障害者権利条約を生かす活動、不適切な指導の改善や合理的配慮、権利の主体としての子どもたちの学びの保障など自治体レベルのとりくみの可能性を、ソーシャルワークの視点から探求する。
目次
序章 子ども条例に基づく子どもの救済
第1章 あらためて「相互信頼」の原理の確立を
第2章 オンブズワークと権利擁護委員
第3章 「是正の勧告」と「改善の要請」
第4章 川西オンブズの思想と実践に学ぶ
第5章 常設の第三者機関の役割の重要性―大津市いじめ事件・第三者委員会の調査報告書から
第6章 「修復的手法」を用いた「修復的実践」
第7章 機能障害のある子どもたちへの「差別」の禁止と「合理的配慮」
第8章 専門職による「不適切な援助・指導」とオンブズワーク
第9章 「自らの判断で調査」「制度などの改善の要請」
終章 「権利学習」の重要性―一人ひとりの子どもたちの幸福のために
著者等紹介
木全和巳[キマタカズミ]
日本福祉大学社会福祉学部教授。主な単著に、『〈しょうがい〉の思春期・青年期の子どもたちと〈性〉―おとなになりゆく自分を育む』(かもがわ出版、2011)、『児童福祉施設で生活する〈しょうがい〉のある子どもたちと〈性〉教育支援実践の課題』(福村出版、2010)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
34
豊田市の子ども条例の制定やその実践から子どものためのソーシャルワークとは何かを考えることができました。子どもの権利条約や障害者権利条約を生かした子どもソーシャルワークとは何なのか、合理的配慮とは何なのか、権利主体としての子どもを捉えるとは何なのか考えながら読みました。子どもを取り巻く関係者が対話を通していくことの大切さも学べました。そして対話を通してエンパワメントしていくことが大切なのだと思います。一つの都市の事例ですが、地域で子どもが主役のソーシャルワークを考えていくうえで考えることが多い内容でした。2018/07/04