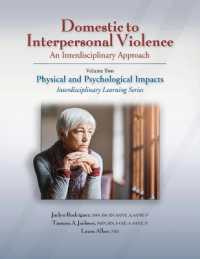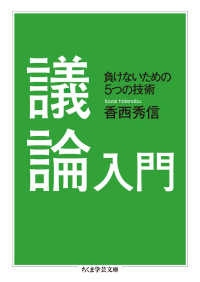目次
第1章 今日の子どもの生活世界とその理解(3・11後を生きる子どもたち―「あの日から」を誰にどう語るか;貧困と孤立のなかで生きる子どもたちの育ちと暮らし―高校保健室で出会い寄り添う ほか)
第2章 子どもと歩む親・援助者のまなざし(不登校支援における親の子ども理解の重要性―親の子ども理解の深化過程に着目して;わが子の“嵐”と向き合う―「非行」と支え合う親たちの子ども理解 ほか)
第3章 教師たちの子ども理解の模索(つらいこともいっぱいある今を、慈しんで子らと生きる―小学生の子どもたち・母親たちとの日々から;生きもがく思春期の子どもにいかに向き合うか―全校教職員による子ども理解のカンファレンス ほか)
第4章 子ども理解の焦点(なぜ、今、自己の育ちに目を向けるのか―「自己の育ち」と子ども理解;「ひきこもり」経験と若者理解―ある青少年自立支援センターにおける若者の声と共同生活の意味を探る ほか)
著者等紹介
田中孝彦[タナカタカヒコ]
武庫川女子大学
片岡洋子[カタオカヨウコ]
千葉大学
山崎隆夫[ヤマザキタカオ]
都留文科大学、元東京・公立小学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
山がち
0
それぞれ筆者の立場が違うせいか、子供観や大人観が異なっているように見えるのが面白かった。理解できない存在として見るか、あるいは理解できるはずの存在として見るのか。大人の無力感、制度や社会への不満など様々なものが渦巻いていて簡単にまとめることができない。その中でも私が印象に残っているのは、子供の感受性の強さである。大人にとっては「得体のしれない」存在であっても、実は自分のことをよく見つめており他者をもよく見ているというのが分かるのである。そして、その感受性を通じて救われる大人の存在というのもまた注目したい。2014/01/17
なお
0
先生、指導員等子供たちに関わる色々な大人が実例を紹介しながら今の子供たちが置かれた状況を述べている。涙なしには読めないような内容もある。普通に会社員をしていると、似たような境遇の同僚と、似たような境遇のご近所さんの中でしか過ごさない。しかし隙間から落ちてしまう人々、特に子供たちがいることを、メジャーではないという理由で見ないのは間違ってる。全ての子供子供が幸せで希望を持てる国であって欲しい。2013/10/08