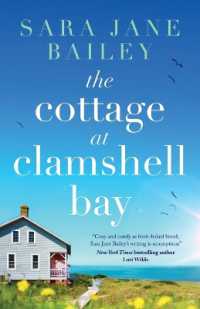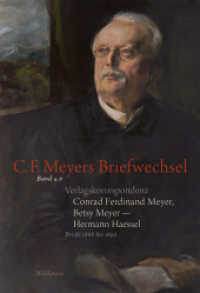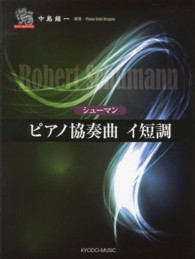- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
目次
言えることばの数と理解力は一致しない
言えても理解できていない
一度に覚えられる単語の数には限度がある
抽象化に問題がある
抽象的な気持ちのことば
疑問詞の理解度を知る
理由が言えない/わからない場合がある
わかりにくい「もしも」の仮定文
振り返る力を知る
感情をコントロールする力〔ほか〕
著者等紹介
湯汲英史[ユクミエイシ]
(社)発達協会常務理事。早稲田大学非常勤講師。王子クリニックリハビリテーション室。言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士
小倉尚子[オグラナオコ]
(社)発達協会指導部部長補佐。早稲田大学非常勤講師。言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士
一松麻実子[ヒトツマツマミコ]
(社)発達協会開発科主任。上智大学・明治学院大学非常勤講師。王子クリニックリハビリテーション室。言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士
藤野泰彦[フジノヤスヒコ]
(社)発達協会開発科科長。王子クリニックリハビリテーション室。言語聴覚士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
riviere(りびえーる)
4
発達障害の子どもは物の見方や感じ方、情報処理の方法や表現に偏りがある。そのため周囲とのコミュニケーションがうまく行かずトラブルを起こしたり学習が進まなかったりして、自分に自信を失うことも多い。この本では発達障害の子どもたちとのコミュニケーション法を27のポイントにまとめて説明。イラストが多くページ数も109Pと薄く読みやすいが内容はエビデンスについても触れてあり著者の経験上のノウハウだけではない。そこが心強い。障害児も健常児も発達の道のりは同じで、進む速度や経路が違うだけだということを改めて感じた。2014/10/05
Asakura Arata
2
大方、日常臨床でのやり方と矛盾していないので、ほっとした。2012/01/05
まさみ
1
大人の文脈ではわかりにくいコミュニケーションになると再認識。2014/03/04