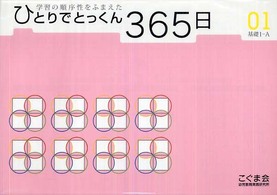内容説明
現実に立ちすくむ若者たち、家族という不思議への問い、そして死の準備とは…希望や幸福を語ることをためらわぬ著者の、社会に向けられた真摯でしなやかなまなざし。最終講義「子どもの本のもつ力」を収録。
目次
不器用な日々「パリ20区、僕たちのクラス」を観る
違和と問いの中で
家族というふしぎ
私たちは、必死にがまんしないできた
四組の夫婦のこと
ひと輝くとき
行方不明の時間
人が物語るということ
幻なき民は亡ぶ
あれが始まりだった〔ほか〕
著者等紹介
清水眞砂子[シミズマサコ]
1941年、北朝鮮に生まれる。児童文学者・翻訳家。2010年3月まで青山学院女子短期大学教授。おもな著作に、『子どもの本のまなざし』(洋泉社、日本児童文学者協会賞受賞)。訳書に、アーショラ・K・ル=グウィン「ゲド戦記」(全6巻、日本翻訳文化賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kiho
7
日常と真摯に向き合ってきた清水さんのこれまでがわかる一冊…不器用な…とは、ごまかさず逃げずそこにいるからこそ…なんだなと感じる☆我慢しないことの大切さと難しさ、何をもって幸せなのか…いろんな問いかけがじんわり響いてくる♪静かに噛みしめたいような、そんな一冊!2013/11/18
舟江
4
断片的には、素晴らしい宝石が散りばめられていたが、根源的な部分が、小生と全く違い。まぶしすぎて、読んでいて非常に疲れた。しかし、考え方の違うしかも異性の方の、本を読むのも悪くないと思えた。 同僚の方々には、さぞかし煙たがられたことであろう。認知症病院の、ボランティア担当の看護師さんの顔が浮かんだ。2021/05/15
joyjoy
3
エッセイ集。「死の準備とはただひとつ、そのことを覚悟すること」、自分にはまだ覚悟はないが、憧れのようなものはあるなぁ。「縁側の陽だまりで」、読みたい本がまた増える。「人が物語るということ」、自分が物語れるものは? 海の記憶が思い浮かぶが、それはにおいや色、揺らぎ、冷たさ、しょっぱさなど、感覚的なものが多くを占め、それらをうまく言葉に出来るかどうかは自信がない。表現できるようになりたい。2020/03/28
ももんが
3
タイトルは不器用となっているが、信念を持って生きてきた作者の強さを感じる本。家族や夫婦、教師のあり方を再考してみてもいいかもしれない。夫婦が「我慢しないで向き合う」という箇所がなかなかいい。伊、映画鉄道員で家族がバラバラになった時「皆が少しづつ我慢したからこうなった」というフレーズを紹介しているが、納得できるような気がする。本の中で紹介されている映画や本も見てみたいと思った。2013/06/16
夏みかん
2
1冊目が良かったので続けて読んでみた。今回は家族についてや夫婦について、そして死についての著者の想いがあれこれ書かれていて、今回もおおいに納得し同意した。それにしても、家族や夫婦ってつくづく距離感の難しい関係だと思う。2018/08/13
-
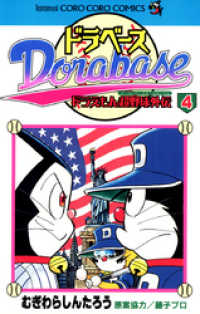
- 電子書籍
- ドラベース ドラえもん超野球(スーパー…