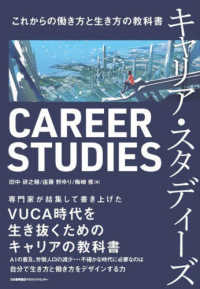目次
第1章 還らなかった画友たち
第2章 喪われたカンバス
第3章 遅れてきた「傍観者」
第4章 戦没画学生との出会い
第5章 無言館とは何か
終章 二人の今、これから
著者等紹介
野見山暁治[ノミヤマギョウジ]
1920年福岡県生まれ。画家、文化功労者。東京美術学校油画科卒。1952年滞仏しサロン・ドートンヌ会員。東京芸術大学教授。『四百字のデッサン』(河出書房新社)で日本エッセイスト・クラブ賞受賞、芸術選奨文部大臣賞、福岡県文化賞、毎日芸術賞受賞
窪島誠一郎[クボシマセイイチロウ]
1941年東京生まれ。小劇場キッド・アイラック・アート・ホール、信濃デッサン館、無言館の各館主。産経児童出版文化賞、地方出版文化功労賞、NHK地域放送文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
16
対談集。野見山氏曰く、戦時下はすべて命令で生きている(29頁)というか、生かされているのだろう。命令される筋合いはない、というのは現代でも勘違いの輩がいるのだが。その輩は人の話を聞く耳をもたないのだ。この対談を拝見すると、自民党の石破氏が「戦争に行かない人は死刑」というのは、本当に恐ろしい言説であると実感する。集団そのものが嫌だ、という野見山氏(58頁)。絵画に描かれた心象風景を推して知るべきなのだ。「産み落とされた」無言館(144頁)。ノーベル賞の小柴昌俊先生もここでの成人式に駆け付けたようだ(口絵)。2013/07/24
Keita
2
無言観設立に関わった2人の半生。二人の波乱ある人生経験にこの様なことはできないと思う。画家の野見山さんの戦時エピソードの「凍土を掘り出てきた氷に閉じ込められた蜜柑の皮の色の鮮やかさに驚きと感動し、絵を描くことの渇望 を感じた」という内容について、戦争は無彩色の人、人の生活の輝きを失わせてしまうものだとつくづく感じる。2023/11/15
HISA
2
数年前に近くで無言館の展覧会があり、いつか長野の無言館に行きたいと思っていて、5月にやっと行くことができた。どういう経緯で無言館が作られたか、二人の率直な言葉でよく分かった。反戦とか大きなものを背負うのでなく、この絵を無くしたくないという気持ち。野見山暁治さんの、何にも確信がないという表現。なんか、分かるような気がした。2023/08/04