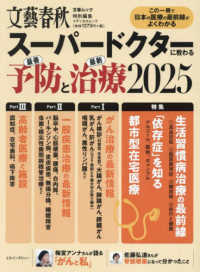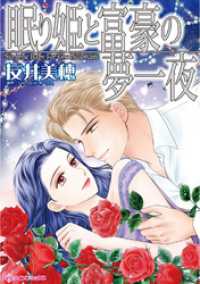目次
第1部 問われているのは子どもの学力なのか(ゆがんだ日本の教育改革論議;PISAとTIMSSが教えてくれていること;つくられた「勉強離れ」;「学びのレリバンス」を回復する)
第2部 フィンランドの教育が照射する日本の教育(フィンランドへの関心の寄せ方をめぐって;学ぶことが生きることに結びつく;学び方を学ぶということ;教育とはなんのため、そして誰のためのもの?;教育は自由の空気のなかでこそ ほか)
著者等紹介
佐藤隆[サトウタカシ]
1957年北海道生まれ。都留文科大学教授。教育学、教育実践学、教師教育論を主な研究領域としている。教育科学研究会事務局長、地域民主教育全国交流研究会『現代と教育』編集長として民間教育研究団体等での活動を通じて全国の教師と交流を深めている。現在は、教師(とくに若い教師)たちが抱えている困難や苦悩の根源に迫ることと、そこに生まれつつある新しい教師像の探求を課題としている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gollum
11
題名が指摘しているポイントは非常にだいじなことだと私も考えるので読んでみたが。左翼系の知識人によくある、日本の現体制への批判に重点が行き過ぎて、フィンランドの教育のすばらしい部分がいまいち浮かび上がってこないのが困ったもんだ。同年代の筆者の考えはとてもよくわかるのだが、やはり、冷静な比較分析で実証的に論じてほしかった。まあ、単純に数値比較できないのが教育の成果だよ、ってことがそうさせてはいるのだろうが。フィンランドの教育についてはこの本でreferしている他の本も読んでみよう。2014/08/02