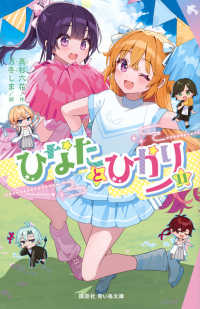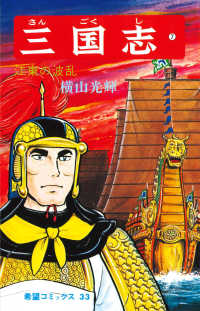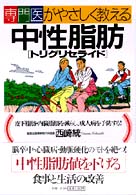目次
第1章 内容分析から計量テキスト分析へ―継承と発展を目指して
第2章 計量的分析の新たなアプローチ―2つのアプローチの峻別と接合から
第3章 新たなアプローチによる分析の手順と実際―漱石『こころ』によるチュートリアル
第4章 手作業による伝統的な方法との比較―新聞記事の分析結果から
第5章 現代における全国紙の内容分析の有効性―社会意識の探索はどこまで可能か
第6章 情報化イノベーションの採用と富の有無―自由回答データを用いた研究事例
第7章 社会調査と計量テキスト分析
第8章 研究事例に学ぶ利用の方策
資料A KH Coder3リファレンス・マニュアル
資料B 機能追加プラグイン「文錦」シリーズ
資料C KH Coderの使用条件とその考え方
著者等紹介
樋口耕一[ヒグチコウイチ]
1978年生まれ。2005年大阪大学大学院人間科学研究科修了。博士(人間科学)。日本学術振興会特別研究員、大阪大学大学院人間科学研究科助教を経て、立命館大学産業社会学部准教授。平成25年度社会調査協会賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
メモ用本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
2
「テキストマイニング入門」にはなかった、「やってみようテキストマイニング」には説明が不十分だった『接合アプローチ』の詳細が記載されていた。 Dictionary-basedアプローチでは、分析者の主観が入り混じってしまう。Correlationalアプローチでは、多変量解析に依存するため、理論や問題意識を自由に操作化して追及が難しい。 その両者のデメリットを補うために、接合アプローチが実施される。 接合アプローチは第一段階の分析で目的達成されれば実施は不要。弱点としては、膨大な紙幅を要すること。(p97)2022/03/21
May
2
日記などのエゴドキュメントで太平洋戦争を振り返るBS番組を見たところに、テキスト分析なる言葉を密林内に見つけたものだから、読んでみた。今後得た知識を生かせる機会があるとは思わないが、テキスト分析なるものの考え方等を知ることができたから目的達成と言ったところ。面白い取組だと思う。こういった分野にもどんどんICTを取り入れるべきだ。なお、計量テキスト分析の実例として、漱石のこころが取り上げられている。こころについての論争(現代文学論争(小谷野)で知った)に一石を投じる内容になっていると思う。2022/02/03
笠井康平
1
お世話になりました2021/01/30
takao
0
ふむ2025/10/27
ごみむし
0
文字ばっかりで読みにくーい(文盲並の感想)。文盲は48ページと49ページだけ読めば良いと思う。夏目漱石の「こころ」についての話が載ってある。唐突に登場人物がドロップアウトしてるわけじゃないぞ、という結論を読んでからなぜそう言えるのかを前に戻って読むと面白いかも。2022/01/22