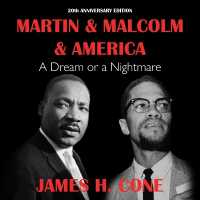内容説明
なぜ集まって働いているのか。制作現場はどのように維持されているのか。綿密な参与観察を通して、労働の実態と「当事者の論理」に迫る。
目次
00 序章:アニメーターの労働への新しい見方―集まって働くフリーランサー
01 アニメーターの労働をめぐる諸前提
02 X社というフィールド
03 生産活動―作画机の上での協働と個人的空間
04 労務管理―仕事の獲得・不安定性への対処・協働の達成
05 人材育成―技能形成の機会
06 個人的空間への配慮と空間的秩序の遂行
07 終章:本書の要約とインプリケーション
著者等紹介
松永伸太朗[マツナガシンタロウ]
一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。法政大学・日本体育大学非常勤講師、(独)労働政策研究・研修機構アシスタントフェローを経て、公立大学法人長野大学企業情報学部助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん
4
インタビューだけでなく、作画スタジオにカメラを持ち込んでデータを収集するなど、松永先生のフットワークの軽さと進取の気性に富んだお仕事には感嘆します。これを成し遂げる交渉力、実行力、持続力は、風聞をもとに自分語りをするだけで何か言ったような気になっている人たちにはまねのできないものでしょう。調査で得たデータを分析し、評価する基準を得るためのアニメ史研究への関心の低さが、個々の結論の妥当性には検討の余地を生んでいるように思います。しかし、例えすべての主張が誤りであっても、本書に記されたデータの価値は不動です。2023/02/05
ぽん
0
やりがい搾取言説を批判する位置づけだった前著と比べるとどうか。本書は問題意識の共有に引っかかる。フリーランスであるにもかかわらず、なぜ集団で働いているのかという問いが出発点。しかし「本来雇用契約を結ぶべきなのに、規制逃れのためにフリーランスを偽装」してる可能性は?安価に済ませるためにフリーランスにしてるんじゃねーの?本書はそういう論点に突っ込んでない。/「この現場に労働時間を短くせよと述べるのは…」(163頁)そもそもアニメーターの待遇改善て時短を叫んでたか?先行研究が少ないために、仮想敵を拵えた感がある2021/01/21
じゅーじゃ
0
初めて社会学を本格的(?)に扱っている書籍を読み切った。最初の先行研究の紹介がかなり難解で今でも理解できたとは到底思えないものの、言葉だけは知っていた「フィールドワーク」がいかにして研究の中で機能するのか、その一例を体験することができたように思う。 2021/01/05
ozanarimakoto
0
実際スタジオに勤めてる身としては極めてリアルな作画現場の像が描き出させれてると感じる。自分は制作なので、制作の側から見える現場もあるけどナ、とは思いつつもやはり興味深い。そういう意味では4章の小林さんのやりとりが興味深い。良きにつけ悪しきにつけだいたい現実はあんな感じだ。実際スタジオ側はべつにぜんぜんアニメーターを搾取したりする「意図」もなければ可能ならよき賃金を用意しようとしさえする。するが、それは本来はフリーランス自身がやることを代替するが故にさの「よき賃金」を本人以外が代替判断することになるし、2020/06/21
-
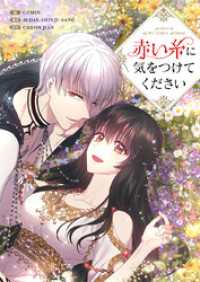
- 電子書籍
- 赤い糸に気をつけてください【タテヨミ】…
-
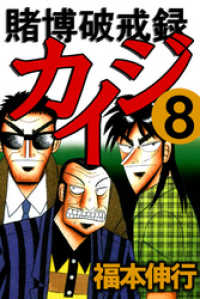
- 電子書籍
- 賭博破戒録カイジ8